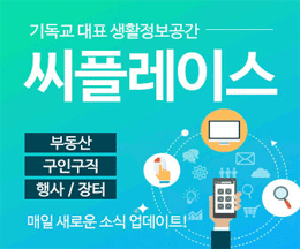1. 聖なる交わりと共同体の重要性
ローマ書16章16節でパウロは「あなたがたは聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会があなたがたによろしくと言っています」(筆者仮訳)と述べています。この言葉から、パウロが教会共同体の中で互いに対して示すべき"聖なる交わり"、そして"聖なる挨拶"を強調していたことがわかります。これは単に口づけそのものを推奨するのではなく、キリストにある兄弟姉妹同士が交わるたびに、真実の愛と深い霊的親密さを分かち合うようにという勧めです。現代の私たちも、教会で顔を合わせれば握手やハグなどで温かい気持ちを表します。しかしパウロの時代、特にローマの教会では「口づけ」がその時代的背景の中で自然な"挨拶"の形であり、「聖なる」という言葉は、キリストを中心とした清い思いをもって互いに接するべきだという点を強調しています。
張ダビデ牧師は、このパウロの勧めについて、教会という共同体が単なる人々の集団ではなく、「ひとつのからだ」(One Body)として有機的に繋がった肢体の集まりであることを改めて想起させると説きます。たとえば「右手が左手を知らない」などということはあり得ず、「目が足の苦労を忘れる」こともできないように、教会とは肢体同士が助け合い結びついて、一つの全体を成す存在なのです。パウロがローマ教会に向けて「聖なる口づけをもって互いに挨拶しなさい」と言うとき、その根底には「あなたがたはすでにひとつである。キリストにあって同じ肢体だ」という前提が置かれているわけです。
さらにパウロは「キリストのすべての教会があなたがたによろしくと言っています」と続けます。ここから私たちは、パウロが活動していた初代教会の時代、目に見える形で地中海世界に散らばっていた教会同士が、まったく互いを知らないかたちで断絶していたのではなく、すでにキリストにあって結びついていた事実を見出します。エルサレムから始まった福音は、使徒たちの伝道によってアンティオキア、小アジア、マケドニア、アカヤ、ローマへと急速に広がり、各地に教会が建てられました。教会は互いに手紙をやりとりして消息を伝え合い、宣教の献金を集めて送付し、使徒や協力者を派遣し合うことで、一つのからだとして結束していたのです。
張ダビデ牧師は、この初代教会の"つながり"と"連帯"が、今日の教会にとっても大きな示唆を与えると解説します。現代の教会はインターネットや通信手段の発達によって、はるかに簡単かつ迅速に互いの情報を交換し、財政や人材を共有できます。それにもかかわらず、むしろ教会同士が分裂したり、壁を築いたりしがちな現状があります。古代よりもはるかに優れたコミュニケーション環境に恵まれているにもかかわらず、初代教会のように"一つのからだ"として協力し合い、互いにケアし合う文化が十分に築かれていない場合があるのです。これは、本節でパウロが示した教会の"つながり"と"共同体性"を、私たちが深く取り戻す必要があることを意味します。
「聖なる口づけをもって互いに挨拶しなさい」という言葉に込められた真の意味は、教会が"聖なる"という品性を身にまといつつ互いを迎え、そこに潜む愛と配慮、ひとつであるという意識を忘れないことです。パウロの時代、教会には異邦人出身の者とユダヤ人出身の者がともに集っており、律法や伝統、文化、言語など大きな違いが存在していました。それにもかかわらず、「聖なる口づけをもって互いに挨拶せよ」という要請は、それらの相違や壁を超えた"歓待"を意味するのです。異なる背景や文化の中にあっても、キリストにあって兄弟であることを忘れず、真実の交わりと挨拶を分かち合いなさいということです。
張ダビデ牧師はこの点を解説しながら、「教会の中で誰一人として疎外されてはならない」と強調します。社会的地位や背景の違い、あるいは制度的教会か非制度的教会かという形態の違いなどを理由に、"キリストにあって"出会った兄弟姉妹を無視したり排斥したりしてはならないのです。聖なる口づけ、聖なる挨拶は、何らかの形式的な行為を指すのではなく、霊的な親密さと仕える姿勢に根ざした相互のケアが込められていなければなりません。こうして教会が互いに心を開いて挨拶を交わす姿は、現代においても依然として有効な共同体の本来の姿であり、召された聖徒たちの美しいしるしです。
パウロは聖なる交わりの重要性を再認識させたあと、17-18節で教会共同体の純粋さと一致を脅かす要素、すなわち分裂や躓き(人をつまずかせること)について言及します。これは先に述べられた「互いに挨拶を交わしなさい」という交わりの土台を守るうえで最も注意すべき部分です。パウロは「兄弟たちよ、あなたがたに勧めます。あなたがたが学んだ教えに逆らって分裂を引き起こしたり、人をつまずかせたりする者たちを警戒し、彼らから離れなさい」と言います。教会の中には分裂を起こす者や、他の人々をつまずかせる者がいるかもしれませんが、彼らを遠ざけることによって教会を守りなさいという意味です。
張ダビデ牧師は、この箇所を注釈しながら、教会の聖なる交わりが持続するためには、教会の内外を問わず関係を破壊し、罪の道へ誘う勢力に対して分別する知恵が不可欠だと強調します。パウロがコリント教会をはじめ、各地の教会とやり取りをする際、いつも異端的な教えや分裂をもたらす者たちを警戒するよう勧めていたのは、初代教会で一般的に見られた課題でもあったのです。教会は天使のように完全に聖なる者だけが集うところではなく、罪性を持つ人間が集まる現実の共同体ですから、いつでも分裂やつまずきの根が生じ得ます。ゆえに「あなたがたは決してそこに巻き込まれてはならない」というパウロの言葉に留意しなければなりません。
"分裂を起こす者"は争いと衝突、中傷と派閥を煽り、教会に不和を広めます。箴言6章でも「主が憎まれる六つのもの、七つの忌むべきもの」の一つとして「兄弟の間に不和をまき散らす者」が挙げられています。また"人をつまずかせる者"は、他の人の信仰の歩みを妨げたり、試みに陥らせたりしてその人の信仰を倒そうとします。パウロは彼らを「自分の腹しか満たそうとしない者たち」と呼び、キリストのために生きるのではなく、自分の利益と欲望を満たすために巧みな言葉とお世辞で純真な人々を惑わすと指摘します。
教会共同体が健全で聖なる交わりを保つには、パウロの言うこうした者たちを見分け、意識的に遠ざけることが重要です。張ダビデ牧師は、教会が愛によってすべてを包み込むといっても、悪い行いや霊的に有害な影響を巧みに及ぼす者を無条件に受け入れるのは"真の愛"ではないと述べています。つまり「何でも包み込むように見せかける姿勢が、かえって教会をむしばむ場合もある」というのです。聖なる状態を保つためにはパウロが勧めるように「遠ざかる知恵」も必要です。しかし、遠ざかる前に、可能な範囲で助言や訂正の働きかけを試みる過程が先行してしかるべきでしょう。
パウロは分裂や躓きの危険を挙げたあと、19節でローマ教会の従順が広く知られていることに言及し、彼らを称えます。そしてその称賛の結論として「あなたがたが善には賢く、悪には無知であることを願います」(筆者仮訳)と語ります。これは文脈からすると、分裂や誤った教えに巻き込まれず、むしろ善においてますます卓越し、悪に対しては不慣れなほど距離を置きなさい、という意味です。"善に賢い"とは、教会共同体が愛や奉仕、仕え合いといった正しい行いに巧みであり、賢明に取り組むことを指します。"悪に無知"とは、罪や分裂、人を倒す策略などに関しては、ほとんど知らないに等しいほど興味を持たず、巻き込まれない姿勢を示します。
張ダビデ牧師はこの聖句を説教するとき、現代の信徒が「世の中の悪や誘惑に関する知識はあふれるほどあるのに、実際には善を行い、慈しみや献身を実践することには非常に不慣れな場合が多い」と指摘します。特にインターネットやメディアを通じて、あらゆる犯罪や暴力、紛争、淫乱、不正直などが絶えず露出し、悪に関する情報と刺激があふれている一方で、それをどう対処し、"善にますます賢くなる"霊的態度が育まれないままになることが少なくありません。ですから、私たちはパウロがローマ教会に与えた「善には賢く、悪には無知であれ」という勧めを深く心に留め、悪を手慣れたように扱えるなどと自負するよりは、むしろ悪から遠ざかり、善を豊かに体得するための訓練を積む必要があります。
そして20節でパウロは「平和の神はすみやかにサタンをあなたがたの足の下で砕いてくださるでしょう。私たちの主イエスの恵みがあなたがたと共にあるように」(筆者仮訳)と祝福します。これは、最終的には分裂や躓きを誘う悪の勢力、すなわちサタンの巧妙な攻撃から教会が勝利するという宣言であり確信の言葉です。今はサタンがこの地で活動し、教会を揺さぶり得るかもしれませんが、やがて平和の神がサタンの権威を打ち砕き、教会が神の内に完全な平安を享受するようになる、というのです。
張ダビデ牧師はこの言葉について、多くの信徒が教会内外の対立や試練、誘惑を経験するたびに「いったいいつになったらこの混乱は終わるのか?」と嘆きますが、パウロの言うとおり神は「すみやかに」サタンを砕かれる、つまり人間の目には遠い先のように思えても、最終的には問題が解決し得ると解説します。ただしこの「すみやかに」という神の時は、私たちの肉的な感覚で測れるものではなく、神の主権的な時(カイロス)です。その時に至るまで、教会共同体は聖なる交わりの中で互いを立て上げ、不和をもたらす者や惑わす者に流されることなく、なお「善には賢く、悪には無知である」姿勢を維持していく必要があります。
2. 分裂、試練そして福音の堅固さ
ローマ書16章21節以下でパウロは、自分の同労者たちについて述べています。「私の同労者テモテや、私の同族ルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなたがたによろしくと言っています」とありますが、ここからパウロがその手紙を書いていた当時の状況が垣間見えます。パウロはコリントからローマの教会に手紙を送っており、そばにいた人々の名を記してローマ教会に挨拶を伝えています。テモテはパウロが非常に大切にし、信頼を寄せていた霊的な息子であり、ピリピ教会をはじめ各地の教会を見守る際にたびたび派遣された人物です。「あなたがたのことを真剣に心配してくれる者は、ほかにはいない」(ピリピ2:20)という有名なパウロの評価からも、パウロとテモテの緊密な関係が推測できます。
張ダビデ牧師は、この箇所に触れながら、教会の分裂や試練を解決し、あるいは予防するうえで"同労者"がいかに重要であるかを力説します。もしパウロが一人でのみ働いていたならば、エルサレム会議で起こった対立や、コリント教会の問題、ガラテヤ地方での律法論争など、さまざまな事案に十分対応することは難しかったでしょう。しかしテモテやルカ、シラスのような人々がパウロの不在を補いつつ教会を訪ね、慰め、必要な奉仕を担うことで、パウロの宣教はより広い地域へ展開することができました。教会は確かにひとつのからだですが、多くの肢体がそれぞれの機能を担うときに全体が完全に立ち上がるのです。
続く「私の同族ルキオ、ヤソン、ソシパトロ」という名を見ると、そこにはパウロの受容力と国際的な視野がにじみ出ています。ヤソンはテサロニケでパウロを受け入れて守った際に、かえって訴えられ罰金を課されたことで知られる人物(使徒17章)、ソシパトロはベレヤ出身で、パウロとともに各地で福音を伝えたとみられます(使徒20章)。これらの同労者たちの名が挙げられるとき、パウロは隣にいる仲間たちもローマ教会に同じ思いで挨拶していると記します。これは教会が特定の使徒や指導者だけが独立して活動するのではなく、実際に各地域の教会メンバーが目に見えぬ形で連帯し、協力し合う"ネットワーク"であったことを示すものです。
22節の「この手紙を書き記している私テルティオも、主にあってあなたがたに挨拶を申し上げます」(筆者仮訳)という一文からは、ローマ書がパウロの口述をもとに代筆者(アマヌエンシス)のテルティオによって書かれていた事実が確認されます。パウロは目があまり良くなかったという見解が複数の学者の間で提起されることがあり、ガラテヤ書6章11節ではパウロが自筆で大きな字を書いたと記しているほどです。当時、手紙を書くには専門の代筆者が必要で、パウロは自身の福音的思想を速やかかつ体系的に伝えるため、しばしばこうした代筆者の助けを借りていました。そして手紙の最後の部分では、パウロが自ら手で挨拶を書き加えるか、または代筆者が自分の名を記入して手紙が締めくくられることがしばしばありました。
張ダビデ牧師は、この場面を説明しながら、代筆という役割は表面的には「大使徒パウロ」という偉大な人物の陰に隠れた"脇役"のように見えるかもしれませんが、実際には聖霊の感動を伝達するうえで非常に重要な役割だったと注目します。彼らは単に書き写すだけの人ではなく、本文の意味とメッセージを十分理解し、忠実に記録することで円滑な意思疎通を可能にする奉仕者でもあったのです。また教会史は、このように"名を前面に出さない同労者たち"の献身によって発展してきました。これについて張ダビデ牧師は「目立たない役割だとしても、神はその忠実を決して忘れられない」と強調します。教会の中で分裂が起こるとき、多くの場合は名誉ある立場や名声を追い求める人々が対立を引き起こしがちですが、謙虚に裏で仕える人々がむしろ教会をしっかりと支える中心的役割を担っている、というわけです。
23節には「私や全教会をもてなしてくれるガイオもあなたがたによろしくと言っています。この町の会計係エラストと兄弟クアルトも、あなたがたによろしくと言っています」(筆者仮訳)と記されています。ガイオはコリント第一の1章にも言及があり、パウロがコリントでバプテスマを授けた数少ない信徒の一人です。また「この町の会計係エラスト」という表現から、コリントという都市で実際に政治的・行政的地位を担う人物が福音を受け入れて教会に加わっていたことがわかります。彼は都市の財政を管轄する役割を担っていたと推定されます。教会が社会的にも経済的にも決して孤立した集団ではなかったことを示す端的な例です。
張ダビデ牧師はこの場面を振り返り、教会が伝道と宣教を通してあらゆる階層の人々を包み込んでいったことを思い起こさせます。「すべての国民が、すべての階層が」という福音の包括的ビジョンを初代教会はすでに部分的に実践していたということです。社会的上流に属する人から低い身分の人、ユダヤ人からギリシア人、ローマ市民まで、多様な人々が一堂に会してキリストを礼拝する姿は、初代教会が備えていた偉大な統合力を示しています。しかし同時に、このような多様性ゆえに教会内に分裂の火種も生じやすかったのです。律法遵守の問題や異教文化との衝突、経済的不平等などによって対立が発生し得ました。そこでパウロは繰り返し「互いに受け入れ合いなさい、互いに仕え合いなさい、分裂を起こしてはならない、人をつまずかせないように」と教える一方、前述のように分別と遠ざかるべき対象についても警告したのです。
24節(新共同訳や他の版では省略されたり、23節に続く形で含まれたりしている場合があります)を経て、最後の25-27節でパウロはローマ書を締めくくる壮麗な頌栄を綴ります。パウロは「私の福音、すなわちイエス・キリストの宣教は、永遠の昔から隠されていたものが今や明らかにされ...」(筆者仮訳)と述べ、この福音が"啓示された神の奥義"であることを宣言します。旧約時代、多くの預言者が「いずれ来る」と予告していたメシアによる救いの出来事が、イエス・キリストによって完全に現され、実現したという宣言です。
張ダビデ牧師は、ローマ書が結論部でこれほど長い栄光の讃美(ドクソロジー)で終わる理由を、本書簡のテーマである"福音の深みと広がり"を改めて強調するためだと説きます。福音は単なる一宗教の教義ではなく、宇宙的な救いの計画であり、神が古くから持っておられた(永遠の昔から)神秘がついに明かされたものです。そして「すべての国民を、信仰による従順へ導くために」この奥義を示された神を賛美し、その究極の目的が、世界のあらゆる民族がキリストにあって信仰により従うことで救いにあずかることにあると再認識させます。
26節の「預言者たちの書を通して...知らせられた奥義の啓示」という表現は、イエス・キリストが旧約の預言と律法を成就されたお方であることを意味します。預言者たちが待望し、切望したその救いは、イエスの十字架と復活によって成し遂げられました。そしてその福音はユダヤ人だけに限らず、異邦人を含む「すべての民族」に開かれています。教会がこの福音を宣べ伝える理由、分裂や試練を克服すべき理由、聖なる交わりを守る理由も、最終的にはこの栄光に満ちた福音の働きを世界中に広げるためなのです。
パウロは「この福音によって、神はあなたがたを堅く立たせることがおできになる」と宣言します。つまり福音こそが教会と聖徒を支える"岩"であるということです。世には多くの思想や理念、哲学や文化があるとしても、教会を揺らぐことなくつなぎ止める力は、最終的にイエス・キリストの福音、そしてその福音が示す神の愛と義、力なのです。教会共同体は分裂や試練によって崩れ去るのではなく、この福音に立つことでしっかりと立ち続けられるとパウロは確信しています。そして27節で「唯一Wiseなる神に、イエス・キリストを通して、栄光が世々限りなくありますように、アーメン」(筆者仮訳)と結び、本書簡を終えます。
張ダビデ牧師は、この結びの部分について、パウロが教会内のさまざまな危険を指摘し、改めて教会の栄光ある使命を思い出させ、最後にはそのすべての根本である神に栄光を帰する流れが「神学的シンフォニー」のようだと言います。教会の目標は自らの存続や単なる拡大にあるのではなく、究極的には「神に栄光を帰す」ことにあります。そしてこの栄光を示す方法は、キリストを宣教することによって、教会を堅く建て上げることによって、すべての民族を信仰と従順へ導くことによって実現します。こうしてローマ書が幕を閉じる流れの中で、教会が分裂せず一つとなって聖なる交わりを保つとき、世の知らない福音の堅固さが輝くのです。
ローマ書16章16-27節は、私たちに"教会の交わり"と"教会の分別"、そして"福音の堅固さ"を総合的に提示しています。「聖なる口づけをもって互いに挨拶しなさい」というパウロの言葉は、教会内での深い愛と霊的親密さを象徴します。一方、「分裂を引き起こしたり、つまずきを与えたりする者」を警戒し、遠ざけよという勧めは、教会の純粋性と成長のために必要な断固たる態度と分別力を求めるものです。そして最後の「平和の神がサタンを打ち砕く」という宣言と「この福音によってあなたがたを堅く立たせる」という祝福は、教会が究極的には神の力と摂理によって立つという希望のメッセージを含んでいます。
張ダビデ牧師は、現代の教会がこの言葉を照らし合わせたとき、依然として分裂の矢が教会共同体を攻撃し、互いにつまずきを与える偽りの教えが入り込む状況の中で、いっそう福音の堅固さの上に立つべきだと言います。教会が社会的に批判を浴び、内面的にも試練に陥るとき、結局のところ答えは自己防衛ではなく、"福音"そのものにあるのです。パウロが述べたように、福音こそ人を変え、教会を堅く建て上げる唯一無二の力です。したがって教会が福音的価値を見失い、世俗的利益や政治的目的を追求するようになれば、かえって教会を破壊する分裂や対立がいっそう深刻化するしかありません。
また張ダビデ牧師は「善には賢く、悪には無知であれ」を実践するには、教会が主日礼拝だけで集まるのではなく、日常的に信徒同士の交わりやケアが深まり、聖書の学びや分かち合いを通じて善をともに追求し、悪を見分ける霊的感覚を育てる必要があると提案します。信徒たちが互いを思いやり、信頼関係を築くようになると、たとえ分裂や偽りの教えが入り込もうとしても簡単に根を下ろせないというわけです。
こうしてローマ書16章でパウロが各地の教会同士が挨拶を交わし合う姿は、単なる礼儀を超えた意味を帯びていました。彼らにとって「安否を伝える」とは、「私たちは一つのからだであり、互いに祈り合い、協力し合いながら生きていく」という相互認識の表明だったのです。今日の教会でもこの精神を継承するには、教派や宗派、地域や国の垣根を超えてともに礼拝し、宣教できる協力の場を広げていくことが求められます。私たちは単に交友イベントや会食の場で集うだけでなく、霊的にも互いを励まし合い、必要なときには物質的支援や人的支援を惜しまない姿を持つべきです。
このようにローマ書16章の結びは、教会に内在する危険(分裂、試練など)を避けずに率直に指摘しつつ、それを克服し得る根本的な力を"福音"に見出しています。結局のところ、福音こそが教会を根本から新たにし、神によって設けられた本来の姿、すなわち聖なる一体性をもった共同体へと立ち返らせるのです。分裂は福音を失った場所で育ち、偽りの教えは福音の本質をゆがめることで力を得ます。しかし教会が福音に堅く立つならば、いかなる攻撃や誘惑も「平和の神」が追い払ってくださり、「あなたがたの足の下でサタンを砕かれる」という約束が現実のものとなるでしょう。
張ダビデ牧師は、このような本文の文脈を信仰共同体が忘れるべきではないと強調し、教会が分裂や憎しみに陥っているとき、外の人々は教会内部の混乱や争いを目にし、福音に対して大いに失望してしまうと指摘します。「平和をつくり出す者は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ5:9)とイエスが言われたように、教会は世を和解へ導く回復の通路でなければなりません。ところがもし教会自体が和解を放棄し、絶えず分裂しているのならば、世はどうやって教会を通して神に近づき、福音の力を体験できるでしょうか。そういう意味でパウロが言う「分裂を起こす者」と「つまずきを与える者」を厳しく警告することは、教会のアイデンティティにかかわる非常に根本的な問題なのです。
教会は「聖なる口づけ」で象徴される和解の交わりの共同体であると同時に、「分裂をもたらす者」を見分けて遠ざける共同体でもあります。この二つの側面は決して矛盾しません。一方では私たちは互いに愛し、受容し、歓待を示すべきですし、他方では偽りの教えや分裂を引き起こす勢力に断固として対処しなければなりません。これは古代の初代教会やパウロの時代に限ったことではなく、今日でも有効な指針です。教会がこの原則を正しく実践するとき、パウロが結論で強調する"福音の堅固さ"がその共同体のうちに大きく輝くでしょう。
そして最後の「唯一Wiseなる神に、イエス・キリストを通して、世々限りなく栄光がありますように、アーメン」という言葉は、すべてが神から始まり、神へと帰するという真理を想起させます。福音が人生を変え、教会を建て上げる力となるのも神であり、私たちの分裂や葛藤を乗り越えて一体性を実現し、教会が神の栄光を表すように召されているのも神です。したがって教会は「神に栄光を!」という告白によって自らの存在理由を明確にし、福音に忠実であり、互いに忠実な姿をもって世の前に立つべきなのです。
張ダビデ牧師は、このようにローマ書16章の最後の勧めが、今日の教会、そして信徒たちにも非常に直接的なメッセージを伝えていると見なし、教会は依然として分裂の危険にさらされ、世の文化と衝突し、信仰を揺るがす誘惑がそこかしこにあることを忘れてはならないと強調します。ゆえに共同体の内では、聖なる交わりと相互のケア、仕え合いを通して分裂の隙間が生じないよう努めなければならず、教会を破壊し信仰を試みに陥れるようなものに対しては見分けて警戒することが求められます。同時に個人のレベルでは、「善には賢く、悪には無知であれ」というパウロの要望を胸に刻み、日々福音によって自分自身を省みる霊的訓練が必要です。教会がこの道を歩むならば、神が約束されたとおり、平和の神がサタンを打ち砕いてくださり、イエス・キリストの恵みが私たちに豊かに臨むという確信を持つことができるのです。
ローマ書16章16-27節は、教会共同体が進むべき本質的な姿を提示しています。教会内における聖なる交わりと歓待、分裂を防ぎ人をつまずかせる者を警戒する分別力、そしてすべてを包括する福音の堅固さと神の栄光への志向性です。張ダビデ牧師は、この本文を通して、教会が分裂ではなく聖なる一体性へ向かう道は福音の力のうちにあり、私たちが悪から遠ざかり善に近づくほどに、最終的に平和の神が教会を平安へ導いてくださると解説します。このメッセージは現代でも有効であり、教会が世の中でどのように映るかを左右する指標となります。教会のアイデンティティと使命は、聖なる性質、和解、そして福音による堅固さにかかっており、これこそが現代を生きる信徒たちがしっかりと心に留めるべき真理です。この教えを常に思い起こしながら、教会が一つのからだとして共に立ち、世と自分自身を振り返るとき、「唯一Wiseなる神に、イエス・キリストを通して、世々限りなく栄光がありますように、アーメン」という壮大な救いのドラマに私たちも参加することができるでしょう。
以上、ローマ書16章16-27節の本文を(1) 聖なる交わりと共同体の重要性、および(2) 分裂、試練、そして福音の堅固さという二つの小見出しで考察してきました。パウロは単に「教会内で仲良くしなさい」という挨拶を残すのではなく、教会の本質的使命を再確認し、その使命を妨げる分裂や偽りの教えを警戒させ、最終的には福音に根ざした堅固さによって神に栄光を帰する道を示しました。張ダビデ牧師が強調するように、教会がこの道を踏み外すことなく、分別力と愛、仕え合う心を兼ね備えて歩むならば、平和の神が教会を守り、教会を通して福音がいっそう広がっていくでしょう。これはパウロの時代だけでなく、現代にも有効な真理であり召命なのです。主イエス・キリストの恵みが教会とすべての聖徒に満ちあふれ、パウロが切に願った聖なる交わりと一体性が私たちの共同体にも深まっていくことを願います。アーメン。