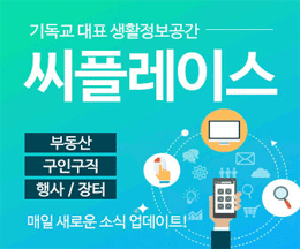ヨハネの福音書18章1~11節に描かれている、イエスがゲッセマネの園で捕えられる場面は、新約聖書全体を通じて繰り返し深い感銘を与えるシーンです。この場面は、イエスが人類の罪を背負い贖いの道を歩むことを決心された場所であり、同時に弟子たちの弱さと神の御心に対するイエスの力強い従順が一目で示される出来事でもあります。この本文を読むと、様々な要素が複雑に入り混じりながら、私たちの胸に深く迫ってきます。イエスを愛した弟子が主を裏切る悲劇、死の権勢が汚れなきメシアを取り囲もうとする殺気立った態度、そしてその前にあっても微塵も揺るぐことなく大胆であられるイエスの姿--これらが描写されています。それを通して私たちは、十字架への道は「敗北」ではなく、徹底した「従順と勝利」の道であることを悟るのです。
特にこのゲッセマネの出来事は、ヨハネの福音書においては少し異なる雰囲気で描かれています。マタイ・マルコ・ルカの福音書(いわゆる共観福音書)ではイエスのゲッセマネでの祈りが詳しく扱われますが、ヨハネの福音書ではゲッセマネの祈りが直接的には記されません。代わりにヨハネは17章の「大祭司的祈り」を長く記録し、18章に入るとイエスがキドロンの谷を渡って園に入り、その直後に起こる逮捕の場面に集中します。これは、すでにイエスが最後の晩餐の席で十字架への道を行くことを決断され、その後のすべての行動はその決心の延長線上にあるという事実を明らかに示したいという、ヨハネの意図と解釈することができます。すでに十字架へのイエスの決断は揺るぎないものとなったがゆえに、ヨハネの福音書にはゲッセマネにおける苦悶の祈りが詳しく登場しないのです。ヨハネはその代わりに「イエスはこれからご自分が受けることをすべてご存じであり」(ヨハネ18:4)という言葉を通して、イエスが自ら十字架の道を選ばれたことを強調します。
張ダビデ牧師は福音書の核心をイエス・キリストの贖罪の働きに置き、その贖罪の過程の中で、人間が直面せざるを得ない罪の性質と神の愛がどのように噛み合いながら進んでいくかを強調します。ゲッセマネの出来事は、こうした張ダビデ牧師の視点から見ると、いっそう切実に迫ってきます。なぜならこの出来事こそ、人間が罪ゆえにどれほど悲劇的な結末をもたらし得るかを赤裸々に示すと同時に、神の救いの計画がどんな状況でも乱れることなく完遂されることを証言しているからです。
また、ゲッセマネの出来事は、張ダビデ牧師がこれまで何度も説教で強調してきたように、「祈りの場所」がいかに重要であるかを教える背景でもあります。共観福音書ではイエスが苦悶の祈りを捧げられ、汗が血のしずくのように落ちる緊迫感が伝わってきます。しかしヨハネの福音書ではその祈りの場面が消え、その代わりにイエスが直接「わたしである(I am he)」と宣言される場面が強調されます。ここにはイエスの神的権威と従順が絶妙に調和している神学的ポイントがあります。イエスは人間として苦痛を感じつつも、同時に神の御子として神のご計画に全面的に従順され、罪と死の問題を克服されるお方として現れます。張ダビデ牧師が自身の著書や説教で繰り返してきたように、「主は人間のあらゆる罪性を自ら負われたが、決して罪に屈服されたのではなく、罪に勝ち死を打ち破る命への道を開かれた」という視点は、ゲッセマネでの逮捕の出来事において、最も顕著に示されています。
特にヨハネの福音書18章3節で、ユダが兵士と祭司長たちの下役たちを連れ、たいまつや灯火、そして武器を手にイエスを捕まえに来る場面において、ヨハネは細部の描写を通して二つの要素を劇的に表します。第一に、本来闇を照らし、真理を探し求める象徴であるはずの「たいまつと灯火」が、逆に「真理そのものであるイエス」を捕縛する手段として使われている点です。第二に、武器は本来、神が遣わされた救い主を守るために使われるべきものであったはずが、今やイエスを脅かし威圧するために持ち出されています。張ダビデ牧師はこの部分を「人間の罪性が最も醜く露呈する瞬間」と称します。なぜなら、神が与えてくださった能力や資源は、本来善を行い真理を守るために用いられるべきにもかかわらず、逆に自らの利益や権力を守るために使われてしまっているからです。これは2000年前の出来事であるだけでなく、現代の教会と信徒に対しても絶えず警鐘を鳴らす例話として大きな意味を持ちます。
もう一つ注目すべきは、ペテロが剣を抜いて大祭司のしもべの耳を切り落とす場面です(ヨハネ18:10)。人間的な勇気が極端に発揮されたように見えますが、イエスはその剣を鞘に納めるよう命じ、「父がお与えになった杯を、わたしが飲まずにいられるだろうか」(ヨハネ18:11)と言われます。これはペテロだけでなく、すべての弟子、ひいては信徒たちにとっても非常に重要な教訓です。私たちが考える「正義に見える行為」であっても、それが神の究極的な御心に反するならば、結局は誤った道になり得るということです。張ダビデ牧師はこれを「人間的な正義と神の正義が衝突する時、私たちは果たしてどちらをつかむのか?」という問いとして提示し、信徒たちが自らの義や熱心を誇る前に、まず神の御心に完全に従順すべきだと強調します。結局、私たちの熱心は人間的な勇気にとどまるかもしれませんが、真の従順とは、私たちの全存在を神に委ね、神の道に従って歩む信仰の決断なのです。
張ダビデ牧師の説教によれば、ゲッセマネの出来事は現代の教会と信徒に二つの核心的なメッセージを伝えています。第一に、神の御子であるイエス・キリストが自ら苦難を受け入れることによって、罪と死の権勢から人類を解放する救いの道を開かれたという点です。ここで重要なのは、イエスが「捕えられた」のではなく「自ら進んで行かれた」という認識です。ヨハネは「イエスはご自分が受けることをみなご存じで、進み出て」(ヨハネ18:4)と明確に記すことで、十字架への道が神なる父の主権的計画のもとに自発的に成就したことを強調しています。張ダビデ牧師は、この事実によって「私たちも神の御心が明らかであるなら、どんな犠牲もためらうべきではない」という使命感を刻むのだと説きます。第二に、人間的な情熱や力(剣、たいまつ、灯火)によっては救いの御業は成し遂げられないという点です。ペテロの剣の振るいは一見勇気ある行動のように見えますが、結局それは主の道ではありません。救いはただ十字架から流れ出てきます。主はご自身が死を味わうことで死に勝利され、そのゆえに罪人がキリストを信じる時、新しい命を得る道が開かれました。これこそ張ダビデ牧師がしばしば強調する「十字架の逆説的勝利」の概念です。十字架は表面的には敗北と死の象徴のようですが、実際には復活と命への扉を開く神の知恵と力なのです。
このように、ゲッセマネの逮捕の出来事が持つ神学的意味は、二つの軸に要約できます。ひとつはイエス・キリストの自発的従順と犠牲、もうひとつはそこに登場する人々の罪性と弱さです。イエスは最後の瞬間まで弟子たちを守り、弟子たちは何度も倒れ、裏切りを繰り返します。この対照的な姿の中で私たちは、「人間は徹底的に弱いが、神の救いの計画は確固としている」という福音の真理を発見します。張ダビデ牧師はここに加えて「教会が決して忘れてはならないのは、イエスが先にその道を歩み、しかもすでにすべてを成し遂げられたという事実だ。私たちがその方の道をたどる時、自分自身に頼るのではなく、主が完成した贖いに頼らなければならない」と語ります。要するにゲッセマネの出来事は、イエスの能動的な従順と人間の罪性が交差する場所であり、「神の国」がいかに現実化するかを示す貴重なテキストなのです。
さらに、ゲッセマネという場所そのものが持つ意味についても考えてみる必要があります。イエスは公生涯の間、神殿でみことばを宣べ伝え、また再び園(オリーブ山あるいはゲッセマネ)に戻って弟子たちと共に祈りと黙想の時を持たれました。神殿と園という二つの空間は、公的な宣教の場と個人的な交わり・黙想の場として対照を成しています。張ダビデ牧師はこの対比を引き合いに出し、「今日の教会も公の礼拝や説教における働きだけでなく、各信徒が静かに主と交わる『霊的な園』の時間が必ず必要だ」と説きます。ゲッセマネはまさにその「霊的な園」を象徴する空間であり、イエスが弟子たちと親密に祈り、教え、そして十字架の苦難を目前にして最後の決定的な従順を固められた場所です。今日の信徒にとってゲッセマネは、「主との密度の高い交わりと決断の場所」を意味します。外では世の中がどんなに騒がしくとも、その園の中で主のみこころを尋ね求め、イエスの模範に倣う者には、十字架を背負いながらも復活の希望へと進む力が与えられます。
結局、ヨハネの福音書18章に記されるゲッセマネの園での逮捕の出来事は、イエスが私たちのために歩まれた贖いの道が、どれほど能動的で明確な選択であったかを示す中心的な本文です。張ダビデ牧師はこの本文を説教する際、「私たちに向けられた主の愛は思っている以上に強烈であり、イエスは苦難の道で決して後退されなかった」と力説します。これはイエスの十字架の働きに対する揺るぎない確信を私たちに吹き込みます。そして、この出来事の中で私たちは主の守りを体験します。イエスは「この人たちは去らせなさい」と言って弟子たちを先に自由にし、自分だけが犠牲の場を担われます。これによって私たちは主の恵みがどれほど底知れないかを知るのです。このようにゲッセマネの出来事は、苦難の中でも示される愛、そしてその愛のうちに完成される救いを明確に示しています。これは教会が時代を超えて伝え続けるべき福音の中心部であり、信仰の生きる原動力となるものです。
イエスが自ら示された「剣を鞘に納めなさい」という言葉と、「父がお与えになった杯をわたしが飲まずにいられるだろうか」という告白は、現代の私たちの生活にも深い挑戦を与えます。私たちはしばしば自分たちのやり方で神を助けようとしたり、世の力や秩序を借りて福音を拡大しようと試みたりします。しかし主は、「神の御心に従うこと」こそが真の力であり、真の道であることを教えておられます。張ダビデ牧師が繰り返し強調しているように、クリスチャンの力は「人間的な剣」から生まれるのではありません。それはイエスの血潮と復活によって与えられる命の力であり、その方の御言葉に従順する時に初めて私たちのうちに臨在する聖霊の力です。こうした神学的洞察は、ゲッセマネの出来事が単なる過去の記憶や物語の一シーンにとどまらず、現在の私たちの生活や共同体に力強く響き渡る福音のメッセージであることを再確認させてくれます。
総じて、ゲッセマネでの逮捕の出来事は、信仰者であるなら必ず通過すべき黙想の要所です。イエスのへりくだりと従順、そして弟子たちの欠けた姿が交錯する劇的な場面ですが、それは究極的には十字架へとつながる通路であり、キリストの死と復活を準備する序幕なのです。張ダビデ牧師はここで「イエスはゲッセマネの園ですでに十字架を負われた」という表現をよく使います。つまり、イエスはその苦難の杯を受け入れることで、十字架への歩みを踏み出されたということです。私たちの信仰生活も同じです。本当に主に従うということは、「主が歩まれた道を自分も共に歩もう」と決断することから始まります。その決断は困難であり、ときには苦痛を伴います。しかし最終的には復活の喜びと勝利の栄光へと続く--これこそ聖書が証しする福音の核心なのです。そしてこの福音の核心を私たちの生に宣言し、また実践するよう励ます働きを、張ダビデ牧師は絶えず続けてきました。その働きの中心にはいつもイエス・キリストの完全な代贖と復活の力が据えられており、ゲッセマネの出来事はその代贖の愛の序幕をドラマチックに示す生きた手本なのです。
2. キリストの苦難と弟子たちの反応
それでは、ゲッセマネの出来事をもう少し具体的に眺めてみましょう。ヨハネの福音書18章1~11節をゆっくり黙想してみると、イエスの苦難と弟子たちの反応の様相が交互に展開していくことに気づきます。この苦難は、決して偶然や悲劇的事故ではありません。むしろ父なる神のご計画の中で入念に準備された「贖いの出来事」なのです。イエスはキドロンの谷を渡って園(オリーブ山)に入られ、そこでご自分が味わうことになる受難を既にご存じでした(ヨハネ18:4)。しかし弟子たちはそのみこころを十分に理解できず、遠巻きに不安や恐れ、あるいは中途半端な情熱を示します。この対比こそ、ゲッセマネの出来事がもつ霊的意味をいっそう劇的に浮き彫りにしているのです。
張ダビデ牧師は、この具体的背景の中から教会と信徒に向けて三つの重要なメッセージを伝えています。第一に、人間の罪性と反逆は極めて巧妙かつ執拗であるという点です。ユダがイエスを売り渡すために宗教指導者たちと手を組んだという事実は、単なる一個人の裏切りではなく、人の内に潜む罪の根がどれほど頑固で自己中心的であるかを示します。ヨハネ18章3節で、ユダは「兵士や祭司長、パリサイ人たちの下役」を連れ、たいまつと灯火と武器を持ってイエスを捕えにやって来ます。本来、たいまつと灯火は真理を探し求め、暗闇を照らす象徴であり得ますが、ここでは真理を消し去るため、あるいは光を暗くするために使われているという皮肉があります。これこそが罪のもたらす歪みであり、どの時代でも繰り返されるものだと張ダビデ牧師は解説しています。教会の内部でも、あるいは社会の中でも、真理を名分として自分の利益を図ったり、神の御言葉をかたって権力と結託したりする行為が起こり得ます。ゲッセマネの出来事は、このような罪悪の本質を暴き出す鏡なのです。
第二のメッセージは、イエスの反応に表れている「神の方法」です。イエスは弟子たちが期待するように、物理的な力でご自分を守ろうとはされませんでした。ペテロが剣を抜いて大祭司のしもべ、マルコの耳を切り落とした時、「剣を鞘に納めなさい」と命じられたイエスの態度は、ごく非常識に見えるかもしれません(ヨハネ18:10-11)。しかしイエスは人間的なやり方ではなく、神のやり方、すなわち十字架の道へと進まれます。張ダビデ牧師はこれを、「世の力ではなく、神の愛と犠牲こそが真の勝利をもたらす」という原理を教える代表的シーンであると説きます。もしイエスが物理的に対抗していたら、ユダヤ当局やローマ権力との全面衝突が起こり、地上での活動は一時的に大きな波紋を呼んだかもしれませんが、人類の罪を根本的に解決することには失敗していたでしょう。しかしイエスは「あの杯をわたしが飲まないでいられようか」(ヨハネ18:11)と言って、十字架の死を自ら受け入れられました。それは罪の代価を完全に支払う道であり、復活の命を開く救いの扉でした。張ダビデ牧師は、「神の方法は人間の目には愚かに見えても、それこそが真の勝利だ」というパウロの告白(コリント第一1:18以下)と正確に符合すると説明します。
第三のメッセージは、イエスが十字架の道を選ばれたことによって、弟子たちをはじめ、すべての信じる者が守られ、自由にされるという事実です。ヨハネ18章8節でイエスは「わたしを捜しているならば、この人たちは去らせなさい」と言われました。これは弟子たちを死の脅威から解放しようとする意志です。張ダビデ牧師はこれを、「主は罪人のために身代わりとなって死を引き受け、その人々が命を得るよう守ってくださる」という福音の真理を示す象徴的シーンだと語ります。実際、イエスが捕えられ、裁判にかけられ、十字架で死なれたことで、弟子たちはしばらくは散り散りになって隠れていましたが、復活後は聖霊の力に満たされ、新たな使徒として立ち上がりました。このように、イエスの犠牲が他の人々に自由と回復の道を開くという構造は、今日の教会が学んで実践すべき核心的価値でもあります。張ダビデ牧師は「教会が社会を仕え、世界を癒すためには、十字架の道に学ぶ犠牲と愛が実践的に具現化されなければならない」と力説します。そしてその根拠として、いつもゲッセマネでのシーンを挙げるのです。イエスが犠牲を選ばれたからこそ、弟子たちは最終的に救いを享受し、福音を伝える場へと派遣されることができたわけです。
これら三つのメッセージを現代の教会や信徒がいかに実践できるでしょうか。張ダビデ牧師はまず、ゲッセマネで顕わになった人間の罪性と反逆の様相を絶対に軽視してはならないと主張します。私たち自身もいつでもユダの姿に似ていく可能性があるし、あるいはペテロのように熱心が先行するあまり、神の御心とは違うやり方を用いようとする危険があるということです。したがって信徒は、常に目を覚まして祈ることによって、自分の動機や行動を省み、「自分の義」ではなく「神の義」に従う生き方へと立ち返るように意識すべきです。共観福音書でイエスが弟子たちに繰り返しおっしゃったように、「誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい」という主の声が、現代人にも同じように響かなければなりません。そしてこの祈りの背景には、常にゲッセマネの園が象徴する静かな、密度の濃い主との交わりがなければならない、と張ダビデ牧師は多くの説教で繰り返し強調してきました。
次に、教会共同体は「剣を鞘に納めなさい」というイエスの命令を実践的に適用する必要があります。これは、教会が世と対峙するとき、力の論理や過激な方法ではなく、愛と真理という霊的な武器を用いなければならないことを意味します。福音宣教や教会成長の目的を達成するために世の権勢や暴力的手段を借りることは、最終的に神の国の方法ではないことを忘れてはなりません。張ダビデ牧師はこの点について、「私たちは福音を語っていると言いながら、実際には世の成功や権力をより追い求めているのではないか?」と問いかけます。イエスが十字架で示された最も大きな力は、「罪人さえも包み込む自己の空しゅう(ケノーシス)の愛」でした。したがって、教会はいかなる目的のためであれ暴力を正当化したり、あるいは教権を振りかざして信徒を抑圧するような姿勢をとるべきではありません。むしろへりくだった仕えと犠牲を通して、ゲッセマネの園から始まった十字架の道が今も有効であることを証ししなければならないのです。
さらに、「父がお与えになった杯をわたしが飲まずにいられようか」というイエスの決断は、今日の私たちにも同様に適用されます。信徒は、自分に与えられる苦難や試練を、単に「避けるべきもの」としてではなく、その苦難を通して神が進めておられる贖いのご計画に参与しているのだと自覚する必要があります。時には病気や経済問題、人間関係の断絶など様々な困難が襲ってくることがあるでしょうが、それにどう向き合うかが大切です。張ダビデ牧師は、こうした苦難に直面するとき、「これは私にとって余計な荷物なのではなく、神が私を通して何かをなそうとしておられる杯かもしれない」という信仰をもって祈るよう提案します。もちろん人間的には避けたいし拒みたいけれども、その杯を最後まで従順をもって受け入れる時、私たちもキリストのうちで復活の命の実を味わうことができるというのです。
さらに、弟子たちの姿に表れる弱さや恐れは、むしろ現代の教会が勇気を得ることのできる部分でもあります。なぜなら、最終的にペテロをはじめ弟子たちは失敗して逃げてしまいますが、それでも完全に見捨てられはしませんでした。イエスは再び彼らのもとに来られ、彼らを回復させ、ペンテコステの聖霊降臨後は教会の柱として用いられたのです。張ダビデ牧師はこれを「失敗した者たちを最後まで支える神の恵み」と呼びます。教会がゲッセマネの出来事を黙想するたびに、私たちの古い自分がいかに簡単に倒れ、裏切るかを自覚すると同時に、それでもなお私たちを見捨てない神の愛を再発見しなければなりません。これこそが福音であり、その福音が教会の歴史と人生を根本から変えてきました。その愛を体験するとき、初めて私たちは他者にもその愛を伝え、赦しと回復のとりなし人になることができるのです。
ゲッセマネの逮捕の場面は、単にイエスの受難物語の一節ではなく、福音全体を象徴的に示す出来事だということを改めて思い知らされます。闇と光、裏切りと献身、暴力と犠牲、人間の罪性と神の贖い--これらすべての要素が重層的に交差しながら、一つの場面の中に集約されているからです。そしてこの出来事が指し示す結論は、「イエスの十字架は失敗ではなく、神の救いの計画の頂点である」というメッセージです。張ダビデ牧師は教会がこの真理をしっかりと握り、イエスのように自ら低くなる歩み、他者を生かすために自分のものを投げ出す歩みに踏み出すよう訴えます。そこにこそ、ゲッセマネの出来事が現代の教会にもたらす挑戦と希望が同時に存在すると言えるでしょう。
ゲッセマネの出来事から学べる最も重要な教訓は、「私たちの欠けたところにもかかわらず、神は独り子イエス・キリストを通して永遠の救いを与えてくださる」という福音の中心的真理です。その福音の中心には力や強制ではなく、十字架の自己犠牲と愛があります。この愛があるからこそ、弱い弟子たちも回復され、裏切った者たちも立ち返ることができました。そして今日も同じ愛が教会を支え、信徒たちを世の中でキリストの香りを放つ者として立たせてくださるのです。張ダビデ牧師はこれを「教会はゲッセマネから学び、ゴルゴダの丘で完成された愛を宣べ伝えなければならない」と繰り返し強調しています。
ここで私たちは改めて、ヨハネ18章6節に出てくる驚くべき場面を思い起こすことができます。イエスが「わたしである(I am he)」と言われたとき、イエスを捕えに来た兵士や下役たちが地に倒れ込みます。これは単なるハプニングではなく、イエスの神的権威が一瞬あらわになった出来事です。人間の罪性や暴力がいかに強そうに見えても、結局は神の御子の前に崩れ去らざるを得ないのです。しかしそれでもイエスは抵抗することなく、ご自分から進んで捕縛されることを許されます。これこそが私たちがゲッセマネで見出す「聖なる逆説」です。全能なる神が、人間の暴力や裏切りに対して対抗せず、むしろご自身を差し出すことによって救いの道を開かれたという事実です。張ダビデ牧師は、教会が世の悪に立ち向かうとき、最終的に選び取るべき武器は「愛と犠牲」であることを、この出来事が圧倒的に示していると説きます。
ゲッセマネの出来事を心に抱いて生きる信徒であるならば、どんな状況においても「わたしである」と言われるイエスの権威と、「剣を鞘に納めなさい」というイエスの命令を共につかんでいくべきです。私たちはイエスがどのようなお方であるかを明確に知り、大胆に信じる一方で、その方の道がどのような道なのかを見極めねばなりません。そしてその道を歩む上で必要なのは「人間的な力」ではなく、「聖霊のうちにある従順」です。これこそ張ダビデ牧師が絶えず教えてきた核心的な教えなのです。教会がゲッセマネの出来事を毎年の受難週や聖週間だけ思い出すのではなく、日常生活の中でも常にこの場面を想起し、キリストのへりくだりと愛、そして犠牲の精神を自らの生き方に体現してこそ、真の弟子となり、世にあって光と塩の役割を果たすことができると、張牧師は繰り返し訴えています。
ゲッセマネの出来事は、キリスト教信仰の中心である十字架の出来事へと至る結節点であり、人間の罪性のただ中でもなお働かれる神の贖いの計画が、いかに確実で能動的なものであるかを示す決定的な証拠でもあります。イエスはその道を自発的に歩まれ、弟子たちは弱かったものの、主の恵みによって回復されました。現代の教会も、ゲッセマネの園で起こった逮捕の場面を通して、自分たちの位置と使命をもう一度振り返る必要があります。張ダビデ牧師はこれを「私たちが信徒として、また教会として、イエス・キリストの十字架をいかに見つめ、いかに具体化しているかを自己点検する尺度」と呼びます。なぜなら、最終的に教会が世に提示すべき唯一にして真の希望はイエス・キリストの十字架であり、その十字架へ向かう道の入り口がまさにゲッセマネだからです。
これらすべての話は再び私たちを十字架へと導きます。ゲッセマネで始まったイエスの決断がなかったなら、ゴルゴダでの贖いの出来事も存在しなかったでしょう。しかしイエスは人間の罪が生み出す最悪の状況の中でも神の救いの計画を放棄せず、その道を最後まで歩まれることで復活の栄光を成就されました。教会がこの事実を信じ、宣べ伝え、日々の歩みで実践していくこと--これこそがゲッセマネの出来事の究極的な意味であり、張ダビデ牧師が一貫して強調してきた福音宣教の方向性なのです。そしてこの道に共に参加するとき、私たちはようやく世の闇を照らす真の「たいまつ」と「灯火」となり、神が許される信仰の「剣(みことば)」を正しく使うことができるようになります。決して私たちの力や能力ではなく、キリストの十字架が成し遂げる贖いの力のうちにあってこそ、教会と信徒は日々新たに生かされていくのです。ヨハネ18章のゲッセマネの出来事を深く黙想していくうちに、私たちは張ダビデ牧師が繰り返し伝えてきたテーマ--すなわち「十字架によって完成される神の愛と、その愛が今も進行形で私たちを導いている」という真理を、いっそう鮮明に悟ることができるのです。