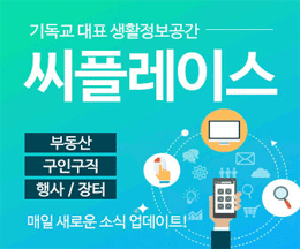1. キリストの苦難と愛の本質私たちは四旬節(サシュンジョル、受難節)の期間、キリストの苦難をより深く黙想すべきです。とりわけヨハネの福音書13章から19章までを受難週に読み進めると、イエス様が受けられた苦難の意味が、いかに深い愛に根ざしているかを改めて発見することができます。教会の伝統において四旬節はキリストの苦難を振り返る時期として位置づけられてきました。人々はしばしば「苦難」という言葉を呪いや裁きと結びつけて考えがちですが、聖書には随所で、苦難がときに神の訓練となり、キリストと共に歩む十字架の道となり得ることが強調されています。張ダビデ牧師もさまざまな説教や教えの中で「苦難こそが愛を深く体験するための重要な通路だ」と述べ、クリスチャンが苦難をどのように捉え、受けとめるべきかを強調してきました。
では、なぜ私たちは苦難を理解しなければならず、なぜ苦難を表面的ではなく深く黙想すべきなのでしょうか。聖書はその答えを明確に示しています。苦難は呪いではなく愛である、と教えているからです。もし愛がなければ永遠の命を知ることはできず、苦難を通して現れる愛を理解できなければ、私たちの信仰も希望も、その根を失いやすいのです。使徒パウロは「信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である」(第一コリント13章13節)と語りました。信仰も希望も大切ですが、愛によって永遠の命が与えられ、その愛の核心はイエス・キリストの十字架と苦難にあります。張ダビデ牧師は「キリストの苦難を通して現れた神の愛を知る道こそが、復活の栄光を目の当たりにする近道だ」と説いています。結局、愛によってもたらされる命、すなわち永遠の命こそ、苦難によって開かれる門だというのです。
ところが私たちの普段の生活や社会の現状を見渡すと、多くの人々が苦難そのものを嫌い、恐れ、ただ避けようとします。実際、韓国社会では長い間3D(Dirty, Difficult, Dangerous)と呼ばれる職種を敬遠する風潮があり、親たちは子どもが苦労しないようにあらゆる努力を注ぎ込みます。無益な苦難をわざわざ買って出ることはもちろん避けるべきですが、「若いうちの苦労は買ってでもせよ」という昔からの言葉が伝える意味は決して軽くありません。そこには、苦難がときに成熟への大切なプロセスとなり得ることが暗示されています。聖書は苦難を通して学ぶ益についてはっきり語っています。たとえば詩篇119篇67節と71節では「苦難に遭う前は私は道を踏み外していましたが、今はあなたの御言葉を守るようになりました。... 苦難に遭ったことは私にとって益となりました。このゆえに私はあなたのおきてを学ぶことができました」と述べられています。ローマ書5章3節以下でも使徒パウロは「患難は忍耐を生み、忍耐は錬達を生み、錬達は希望を生み出すことを知っている」と語り、苦難がどのように私たちの人格と信仰を鍛錬するかを詳しく述べています。
張ダビデ牧師はローマ書5章のこのくだりを、数多くの説教で頻繁に引用します。患難と苦難に対する私たちの姿勢がどうあるべきかを、「苦難のトンネルに入るとき、主の愛と共に歩みなさい。その道を一人で行くのだと思わないで、決して負いきれない重荷を与える神ではないことを忘れないように」と勧めるのです。これは単に「苦難をただ耐え忍びなさい」という受動的な勧めではなく、苦難自体が新しい命と復活の希望へ導く道であることを説得力をもって示すメッセージです。
さらに聖書は「キリストと共に苦難を受けなさい」(ピリピ1章29節)、「福音と共に苦しみを受けなさい」(第二テモテ1章8節)、「キリスト・イエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください」(第二テモテ2章3節)とも告白しています。そして「善を行うことで苦難を受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に尊いことです。... キリストもあなたがたのために苦難を受け、その模範を残されました」(第一ペテロ2章20-21節)ともあり、苦難はキリストに似る道であり、キリストの足跡にならう道であると強調します。使徒たちは苦難から逃れよとは言いませんでした。むしろ苦難が「キリストの残された苦しみにあずかる道」(コロサイ1章24節)であると教えたのです。張ダビデ牧師もこれらの聖句に基づき、「私たち一人ひとりの人生に訪れるあらゆる苦難は、最終的に神の愛を広げる道具になり得る。問題は私たちの視線がどこを向いているかだ」とよく語ります。
しかし現実を見ると、今日の教会の中でも「苦難なく信仰生活することこそ正しい」とされてしまう風潮が時に見られます。さらには、ある人が苦難に遭うと、それを神の呪いや裁きだと見る視線も根強く存在します。もちろん、自ら無益な苦難を招くのは愚かな行いですが、クリスチャンであるなら主の苦難にあずかることで、その愛が何たるかを体験しなければならないのが聖書の教えです。けれども教会が苦難を否定し、福音そのものを「苦難なし」の形で取り繕って伝えようとするとき、信仰は軽薄になり、愛は表面的な次元にとどまってしまいます。実際、教会の中でも少しでも大変なことが起きれば、すぐ背を向けたり恨み言を言ったりする場面を目にするとき、キリストの血潮の愛、苦難を通して示された濃厚な犠牲と献身の愛が果たして私たちの内に生きているのかを顧みざるを得ません。
張ダビデ牧師は、教会が軽薄になり下品になってしまった原因を「十字架の苦難を十分に教えてこなかったからだ」と指摘します。キリストの苦難は神の裁きや法的刑罰だけの問題ではなく、人間の罪と対峙したとき、神の愛が示す最も劇的な形態だというのです。彼は「苦難こそが真の愛を悟る試験場だ」と語ります。教会がこの点を回復するとき、すなわち苦難に対する正しい理解と教えが回復されるときこそ、真の復活の力が現れるという事実を忘れてはならないと強調します。イエス様の苦難を個人的な罪悪感や刑罰の次元だけで解釈する短絡的な視点にとどまらず、十字架の犠牲が示す感動、その犠牲の中で結実する復活の栄光を共に体験すべきなのです。
ヨハネの福音書13章1節を見ると、キリストの苦難が本格的に始まる場面について次のように記されています。「さて、過ぎ越しの祭りの前に、イエスはこの世を去って父のもとへ行くご自分の時が来たことを知り、この世にいるご自分の弟子たちを愛して、彼らを最後まで愛し抜かれた。」 ヨハネ福音書ではイエス様の受難物語が他の福音書よりも長く記録されています。13章から16章にはイエス様の長い別れの説教が、17章には別れの祈りが、そして18章以降で実際の受難事件が展開されます。しかしこの一連の苦難の始まりにあって、ヨハネが注目する言葉は「愛」であり、「最後まで愛された」ということです。ある意味、「愛」とは最も大きな苦難になり得ます。愛とは、苦難を覚悟しなければならない道だからです。
仏教の教えの中には「愛するな、愛(愛着)は即ち苦である」というような教えがあります。執着を生むという観点で、その結論に至るわけです。しかしキリスト教の視点は異なります。十字架の惨たらしい死はイエス様にとって最も苛酷な苦難でしたが、同時にそれは最も偉大な愛の出来事でもありました。だからこそ私たちはキリストの苦難を傍観するのではなく、「キリストの苦難にあずかりなさい」と招かれています。まさにピリピ書3章10-11節で使徒パウロが語るように、キリストの復活の力と苦難にあずかることによって復活に達しようとする道が、私たちの前に用意されているのです。
私たち人間の本能的な性質として、自分が困難な状況に陥れば、他者に目を向ける余裕などなくなりがちです。その状況で愛は贅沢に思われ、自分を憐れみ、自分中心に考えやすくなってしまいます。ところがイエス様は死の影が迫る最後の瞬間まで、弟子たちを「最後まで」愛されました(ヨハネ13章1節)。これは私たちに「困難な状況ほど、むしろ他者のための愛がいっそう必要になるのだ」という事実を気づかせてくれます。張ダビデ牧師はこの箇所をしばしば引用し、特に「イエスはご自分が世を去って父のもとへ行かれる時が近づいていると知りながら、最後まで弟子たちを愛された」という一節に注目します。人間の心では想像しがたいアガペ的な愛が、ここで極みに達しているのだと語るのです。
さらにヨハネ福音書13章を深く理解するには、マタイ福音書20章やルカ福音書22章もあわせて読む必要があると言われます。これらの箇所には、弟子たちが誰が偉いかをめぐって争っていた様子が記録されており、それがまさにヨハネ福音書13章でイエス様が弟子たちの足を洗われる出来事とつながる背景となっています。マタイ福音書20章20-23節では、ゼベダイの子たちの母がイエスのもとに来て、「一人はあなたの右の座に、もう一人は左の座につかせてください」と願います。イエスはその座は「与えられるもの」であって「求めて得るもの」ではないというように答えつつ、十字架の杯を飲む覚悟があるかを問いかけます。
ここで十人の弟子たちは、その二人の兄弟に憤慨します(マタイ20章24節)。「どうしてあんなにも高慢に高い地位を要求できるのか」といった怒りだったでしょう。しかしイエスは「異邦の支配者たちが権力をふるうのは世のやり方」であり、「あなたがたの間ではそうであってはならない。あなたがたの中で偉くなりたい者は仕える者になれ」と教えられます(マタイ20章25-27節)。そして「人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、多くの人の身代金としてご自分の命を与えるためである」(マタイ20章28節)と語り、ご自身の生涯そのものが「仕えること」そのものだったと示されます。張ダビデ牧師はこの箇所に触れるとき、「言葉と行いが完全に一致した仕え方をできるお方は、イエス・キリストだけだ。私たちの愛が口先だけにとどまる瞬間、私たちはすでに十字架の道から遠ざかっているのだ」と説明します。
ルカ福音書22章14-15節を見ると、イエスが「わたしが苦難を受ける前に、あなたがたと共にこの過越の食事をすることをどんなに望んでいたことか」と言い、最後の晩餐を準備される場面が出てきます。しかしその晩餐の席ですら、弟子たちの間では「誰が一番偉いか」という争いが起こります(ルカ22章24節)。ルカはこれを「彼らの間に争いが起こった」と率直に記録していますが、これこそがヨハネ福音書13章でイエス様が弟子たちの足を洗って「仕えること」とは何かを、直接身をもって示された歴史的背景なのです。張ダビデ牧師はこの事件をめぐって、「弟子たちは主のそばにいながらも、依然として世の観点で地位を欲していた。主はそうした弟子たちを叱って諦める代わりに、むしろ足を洗い与える徹底した愛で仕えることを教えられた」と述べます。
晩餐の終盤、イエスはパンとぶどう酒を弟子たちに手渡し、「これはあなたがたのために与えられるわたしのからだである。これを行ってわたしを記念しなさい」(ルカ22章19節)と仰せられます。ぶどう酒に関しても「これを飲みなさい。これは罪の赦しを得させるために多くの人のために流す、わたしの血、すなわち契約の血である」(マタイ26章28節)と語られます。これは十字架の犠牲の深い意味を予表する象徴ですが、そうまで語られた直後でさえ、弟子たちは「誰がより偉いか」をめぐって争いを続けます。これは人間の罪性と愚かさを余すところなくさらけ出す場面でありながら、それでもなお彼らを「最後まで」愛するイエス様の深い姿が、いっそう際立つ場面でもあります。
張ダビデ牧師は、弟子たちの争いが示す真実について「最終的に人間の罪性は、神の愛が最もドラマチックに表される瞬間にさえ、自分が高くなろうとする欲望をむき出しにする。しかしその暗闇を照らす光こそ、主の仕える姿であり、それがキリストの苦難を通じて完成された愛である」と説きます。このような文脈において、苦難は「愛の指標」です。苦難があるからこそ、愛が本物かどうかが明らかになり、苦難を通して愛は鍛えられ、深まっていきます。
イエス様は弟子たちの争いを収めるために叱責するのではなく、静かに腰に手ぬぐいをまとい、たらいに水を注いで彼らの足を洗われました(ヨハネ13章4-5節)。当時のパレスチナの道は砂埃が多く、一般的な履物は今日のサンダルに近いものでした。人々はほぼ素足に近い状態で生活していましたから、一日外で働いて帰ると足が非常に汚れるのが日常でした。裕福な家ならば、主人の客人の足を奴隷が洗うことが自然だったのですが、ここではむしろ主人であるイエスが弟子たちの足を洗われたのです。弟子たちは自分が「仕えられる立場」にあると勘違いしていたのに対し、イエスは彼らの主でありながら、僕の立場に下って仕えられたのです。
これこそが真の愛であり、「最後まで愛された」姿でした。今日、教会が最も回復すべき愛の形こそ、この「へりくだりの愛」です。張ダビデ牧師はこの教えを引用し、教会が表面上「愛」を語りながらも、実際には互いの足を洗うどころか、誰がより教会で評価されるか、誰がより「信仰が厚い」と思われるかを競争する姿を嘆くべきだと強調しています。真の愛とは、その相手の反応や態度に関係なく、最後まで責任を負おうとする心であり、それこそがキリストの苦難から流れ出る愛の本質なのです。
仕えることは決して容易なことではありません。愛は苦難を伴います。イエスが弟子たちの足を洗われたとき、弟子たちは羞恥心と同時に啓示を得たことでしょう。だからこそイエスは「わたしが主であり、また師であるのに、あなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたも互いに足を洗い合うのがふさわしい」(ヨハネ13章14節)と命じられます。仕えることはすなわち愛の実践であり、キリストのもとで偉くなりたいと望む者は必ずへりくだって僕(しもべ)となるべきだという点をはっきり示されたのです。私たちの信仰生活も、この視点で再解釈される必要があります。信徒であれば誰でも、もっと楽になりたい、認められたい、高く評価されたいという思いが出てくるでしょうが、そのたびに十字架に示されたイエスの苦難と仕える姿を黙想すべきです。張ダビデ牧師は「主の御心にかなう愛を切に求めるなら、最終的に私たちが進むべき道は仕えの道、つまりへりくだりの道だ。苦難を避けた瞬間、愛も遠ざかりやすい」と強調します。
このように、苦難は愛を証明し、愛は苦難の中で完成します。イエス様が弟子たちの足を洗われた場面は、結局十字架の愛を予告するものです。十字架は全宇宙的な苦難であると同時に、全宇宙的な愛の出来事でもあります。そして聖書は、その「苦難にあずかれ」と私たちに求めています。教会が苦難を教えるとき、教会は軽薄で表面的な愛ではなく、深く濃い犠牲的な愛を実践する共同体へと変わることができます。そうなるとき、キリストにあって栄光の復活へと至り、世は真の教会の価値を見いだすようになるでしょう。
________________________________________
2. 苦難にあずかる信仰と教会の刷新私たちの信仰の歩みにおいて、「苦難にあずかる」とはキリストと共に十字架を担うことを意味します。見た目には非常につらく険しい道です。しかし逆説的にも、この道こそが真の自由と喜びにつながります。ピリピ書3章10-11節でパウロは「わたしはキリストとその復活の力と、その苦難にあずかることを知りたい。その死の状態にまで自分を同形化して、何とかして死者の中からの復活に達したい」と告白します。ここで「その復活の力」と「その苦難にあずかること」を同じ文脈で言及している点は非常に印象的です。復活の力がキリストの苦難からかけ離れた出来事ではなく、むしろ苦難にあずかることによって一層具体的に体験される力だということだからです。
教会史において数多くの信仰の先人たちは、苦難を恐れるよりも、苦難を通して得られる霊的益と復活の力を確信して歩んできました。たとえば殉教者たちの歴史は、苦難の究極的な実りが何であるかを私たちに力強く示します。彼らは断じて自ら進んで苦痛を求めたり、死を美化したわけではなく、福音のためであれば、どのような患難をも恐れないことを証明しました。「キリストの残された苦しみを、その体である教会のために自分の肉体に満たしている」(コロサイ1章24節)というパウロの告白も、教会を仕えるための犠牲が、ときに避けられない苦難を意味することをよく示しています。
張ダビデ牧師は、このような苦難の神学が個人の霊性にとどまらず、教会の刷新にも決定的な役割を果たすと強調します。「もし教会が苦難を忌避し、痛みを見て見ぬふりをし、人生の重荷を負おうとしないならば、その教会は地上で十字架を証しできない共同体となってしまう。教会がこの社会の中で世の光と塩の役割を果たすには、イエス様が語られた狭い道を大胆に歩む覚悟が必要だ」という教えです。教会が世と妥協し、苦難を安易に避けようとすればするほど、教会の霊的力は失われてしまいます。したがって苦難に対する私たちの姿勢は、単に個人の信仰の問題にとどまらず、教会のあり方にも直結する問題なのです。
教会が世の中においてイエス・キリストの愛を示すというとき、それは具体的な生き方の中で表されねばなりません。福音を伝える中で起こる軋轢や、イエス様の精神に反する世の潮流に立ち向かうことで生じる衝突、そして善い行いをしようとする際に受ける反対や不利益などがその例となるでしょう。私たちが職場や家庭、あるいは社会のさまざまな領域でキリストの精神に従って生きようとするなら、必然的に「小さな十字架」が伴います。これを拒まずに喜んで担うとき、私たちはイエス様の苦難に少しずつあずかることができます。同時に、その道のりの中で「復活の力」を経験するようになるのです。
ヨハネ福音書13章での足を洗う出来事は、単なる儀礼的教育や倫理的教訓を超えて象徴的な意味を持ちます。イエス様は弟子たちの足を洗いながら、「わたしがあなたがたに行ったように、あなたがたも行うように」(ヨハネ13章15節)と明確にお示しになりました。これは互いに足を洗うという愛の実践が、教会共同体の内で広がらなければならないことを意味しています。もし教会の中で「誰がより高い地位にいるか」「誰がより評価されるか」をめぐる争いが起こるなら、それはすでに最期の晩餐の席で弟子たちが見せた過ちを再現しているようなものです。しかし私たちは主が示された道を歩まねばなりません。まず自ら低くなる者こそ、最終的には最も高くされるという原理、終末論的価値観の転換が教会のうちに根づくとき、真のリバイバルが起こるでしょう。
したがって苦難なしに栄光だけを求めたり、無条件に安楽と繁栄だけを願う信仰姿勢は、実のところ福音の本質から逸脱する態度です。聖書は「狭い門から入りなさい」(マタイ7章13節)と教えます。広い門、楽な道は滅びに至るという警告があるのです。ここでいう狭い門、狭い道には必然的に犠牲と苦難が伴います。だからこそ十字架を負われるイエスを目撃した弟子たちは、当初その道を共に歩むことを恐れて逃げましたが、最終的に聖霊の力の中で十字架の意味を悟り、喜んで殉教の道をさえ歩むようになります。キリストの苦難を共に担うことが、どれほど栄光に満ちて尊いことかを悟ったからです。
しかし現代の多くの教会や信徒の間には、「繁栄の神学」あるいは「成功の神学」の影が色濃く残っており、いまだ苦難を否定的にしか理解できない傾向があります。祝福と言えば、物質的に恵まれ、健康で豊かになることばかりを思い描き、病や困難に陥ったときは祝福とは見なさないのです。しかし聖書は苦難のただ中にあっても、いくらでも祝福が下ることを幾度も強調しています。旧約のヨブの物語は、極度の試練の中でも神を信頼する人に与えられる回復と倍化の祝福を示しますし、詩篇をはじめ多くの箇所で、苦難を通して神をより深く知る恵みが明かされています。
張ダビデ牧師は「苦難それ自体が嬉しかったり甘かったりするわけでは決してない。しかし私たちが苦難を見る視点が変わるとき、それは成熟と復活への契機となる。私たちがもう一度、主の心を学ぶ機会となる」と説きます。そういうわけで教会が苦難について正しく教えるとき、信徒たちは揺るがない信仰、主に深く根を下ろした希望、そしてどのような状況でも愛を手放さない霊的成熟へと進むことができます。そしてそうした信徒たちの集まりである教会こそ、世の目に「軽い存在」ではなく、「まことに重厚で聖なる共同体」と映ることでしょう。
ヨハネ福音書13章1節から始まるイエス様の苦難の物語は、「最後まで愛された」という言葉で代表されます。これは終わりの時まで愛するという意味であり、いかなるものにも揺るがない絶対的な愛を意味します。私たちがその愛を生きて実践するとき、教会の内でも世の中でも、イエスの香りが広がるのです。愛のゆえに生じる苦難を恐れないようにと、聖霊は日々私たちに新たな力を注いでくださいます。
さらに言えば、教会の刷新は、この「苦難にあずかる信仰」がどれほど共同体の中に根づいているかに直結しています。もし教会内で争いと分裂、誤解や対立が絶えず、お互いに仕え合うより自分を高めることに忙しいとしたら、それはすでに苦難を回避しようとする態度から、愛が冷えてしまった結果だと言えるでしょう。張ダビデ牧師は多くの説教で「十字架の道から離れないでください。その道が孤独で苦しくても、聖霊の助けがあるとき、むしろ私たちの魂はその道で自由と平安を体験するようになるのです」と何度も強調しました。教会の中でも個人の生活においても、苦難に対する私たちの態度は、そのまま愛に対する態度であり、この二つは切り離せない関係にあるというメッセージです。
結局、教会が復活の栄光を真に味わうためには、十字架の苦難をただ傍観するのではなく、その中に参与する共同体とならなければなりません。弟子たちの足を洗われた主の姿を思い起こし、互いの足を洗い合えるような小さな実践を通して、苦難にあずかることを学ぶ必要があります。それは単に礼拝堂の中での儀式や式典にとどまらず、家庭や日常、社会の中で、弱り果てた人々を助け、自己の快適さを手放し、ときに誤解や損失を覚悟しながらも真理を守り抜くプロセスとして具体化されていきます。このような姿勢は決して容易な道ではありません。けれどもこれこそが、本当の意味で教会が示すべき姿であり、世が教会に望んでいる聖なる影響力なのです。ヨハネ福音書13章以降を丹念に黙想してみると、「愛して、愛し抜かれた」イエス様の姿が一貫して強調されます。そして17章に至ると、イエスは別れの祈りを捧げられながら、弟子たちが世から隔絶されることなく、しかし世の中でも清く保たれるように祈っておられます(ヨハネ17章15-17節)。世のただ中で、世が与え得ない喜びを持ちながら、キリストの証人として生き抜くようにと願われるのです。これが可能になるためには、どのような苦難に遭おうとも、主の愛に根を下ろして揺るがないことが必要です。
張ダビデ牧師は「世にあっては苦難がある。しかし勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝ったのだから(ヨハネ16章33節)」というイエス様の御言葉にある「勇気を出しなさい」という命令に注目すべきだと語ります。この「勇気」は、聖書がいうところの「苦難に立ち向かって戦え」という単純な気合ではなく、すでにイエス様が苦難と死に勝利されたという事実に基づく、信仰の平安です。苦難に遭っても揺るがない理由は、イエス様が既に勝利されたからなのです。教会はまさにこの福音的な勇気を携えて世へと派遣された共同体です。そしてその勇気を特徴づける最も大切な印が、「最後まで愛する仕えの姿勢」なのです。
愛ゆえにもたらされる苦難こそ、イエス様の生涯を最も生き生きと示す姿です。イエス様が苦難を選ばれたのは、私たちに対する徹底した愛のためでした。これは教会においても同様に適用されます。私たちが「互いに愛し合う」と告白するとき、その愛は口先だけではなく、自らを犠牲にしてへりくだり、仕えようとする具体的な行動を伴わなければなりません。その道に苦難が伴うとしても、その苦難を通して主の栄光が現れるのです。
結論として、キリストの苦難にあずかる信仰は、私たちを真の愛の道へと導き、教会を表面的な宗教組織ではなく、まことの神の共同体として刷新します。張ダビデ牧師はこのような苦難の神学を「私たちをイエス様とさらに親密に結びつける通路」と呼び、「苦難が深まるほど、キリストの愛は一層鮮明となり、私たちの信仰は新たな力を得て復活の栄光にあずかるようになる」と強調してきました。だからこそ私たちは四旬節を過ごすにあたって、あるいは受難週に特別にヨハネ福音書13章から19章までをじっくり黙想し、イエス様の愛がどれほど深い苦難を通して示されたかを悟らなければなりません。そしてその苦難の道を、いとわずに最後まで歩まれた主の仕えの姿を見習うことを決意すべきです。
弟子たちの足を洗われたイエス様、そして十字架の上で決して諦めることのなかった愛は、今も教会に向かってこう語りかけておられます。「わたしはあなたがたを愛し、最後まで愛し抜いた。だからあなたがたも互いに足を洗いなさい。世に出て行って、苦難を避けるのではなく、愛を選び取りなさい」と。苦難を通して明らかにされる、真摯で濃厚な愛が回復されるとき、教会は再び立ち上がり、世は福音の力を新たに体験するでしょう。そしてその先に復活の栄光が待っていることを、私たちは確信するようになるのです。
これこそが四旬節、あるいは生涯を通じた信仰の歩みの中で、私たちが心に留めるべき核心的な真理であり、同時に張ダビデ牧師が繰り返し強調してきたメッセージでもあります。「苦難なしに十字架はなく、十字架なしに復活もない」ということを真に悟るとき、教会はようやく初代教会が享受していた力と感動を取り戻すでしょう。そして個人の生活においても、私たちがイエス様の苦難にあずかるとき、愛からもたらされる力がどれほど強力であるかを全身で体験することになるのです。
1. キリストの苦難と愛の本質私たちは四旬節(サシュンジョル、受難節)の期間、キリストの苦難をより深く黙想すべきです。とりわけヨハネの福音書13章から19章までを受難週に読み進めると、イエス様が受けられた苦難の意味が、いかに深い愛に根ざしているかを改めて発見することができます。教会の伝統において四旬節はキリストの苦難を振り返る時期として位置づけられてきました。人々はしばしば「苦難」という言葉を呪いや裁きと結びつけて考えがちですが、聖書には随所で、苦難がときに神の訓練となり、キリストと共に歩む十字架の道となり得ることが強調されています。張ダビデ牧師もさまざまな説教や教えの中で「苦難こそが愛を深く体験するための重要な通路だ」と述べ、クリスチャンが苦難をどのように捉え、受けとめるべきかを強調してきました。
では、なぜ私たちは苦難を理解しなければならず、なぜ苦難を表面的ではなく深く黙想すべきなのでしょうか。聖書はその答えを明確に示しています。苦難は呪いではなく愛である、と教えているからです。もし愛がなければ永遠の命を知ることはできず、苦難を通して現れる愛を理解できなければ、私たちの信仰も希望も、その根を失いやすいのです。使徒パウロは「信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である」(第一コリント13章13節)と語りました。信仰も希望も大切ですが、愛によって永遠の命が与えられ、その愛の核心はイエス・キリストの十字架と苦難にあります。張ダビデ牧師は「キリストの苦難を通して現れた神の愛を知る道こそが、復活の栄光を目の当たりにする近道だ」と説いています。結局、愛によってもたらされる命、すなわち永遠の命こそ、苦難によって開かれる門だというのです。
ところが私たちの普段の生活や社会の現状を見渡すと、多くの人々が苦難そのものを嫌い、恐れ、ただ避けようとします。実際、韓国社会では長い間3D(Dirty, Difficult, Dangerous)と呼ばれる職種を敬遠する風潮があり、親たちは子どもが苦労しないようにあらゆる努力を注ぎ込みます。無益な苦難をわざわざ買って出ることはもちろん避けるべきですが、「若いうちの苦労は買ってでもせよ」という昔からの言葉が伝える意味は決して軽くありません。そこには、苦難がときに成熟への大切なプロセスとなり得ることが暗示されています。聖書は苦難を通して学ぶ益についてはっきり語っています。たとえば詩篇119篇67節と71節では「苦難に遭う前は私は道を踏み外していましたが、今はあなたの御言葉を守るようになりました。... 苦難に遭ったことは私にとって益となりました。このゆえに私はあなたのおきてを学ぶことができました」と述べられています。ローマ書5章3節以下でも使徒パウロは「患難は忍耐を生み、忍耐は錬達を生み、錬達は希望を生み出すことを知っている」と語り、苦難がどのように私たちの人格と信仰を鍛錬するかを詳しく述べています。
張ダビデ牧師はローマ書5章のこのくだりを、数多くの説教で頻繁に引用します。患難と苦難に対する私たちの姿勢がどうあるべきかを、「苦難のトンネルに入るとき、主の愛と共に歩みなさい。その道を一人で行くのだと思わないで、決して負いきれない重荷を与える神ではないことを忘れないように」と勧めるのです。これは単に「苦難をただ耐え忍びなさい」という受動的な勧めではなく、苦難自体が新しい命と復活の希望へ導く道であることを説得力をもって示すメッセージです。
さらに聖書は「キリストと共に苦難を受けなさい」(ピリピ1章29節)、「福音と共に苦しみを受けなさい」(第二テモテ1章8節)、「キリスト・イエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください」(第二テモテ2章3節)とも告白しています。そして「善を行うことで苦難を受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に尊いことです。... キリストもあなたがたのために苦難を受け、その模範を残されました」(第一ペテロ2章20-21節)ともあり、苦難はキリストに似る道であり、キリストの足跡にならう道であると強調します。使徒たちは苦難から逃れよとは言いませんでした。むしろ苦難が「キリストの残された苦しみにあずかる道」(コロサイ1章24節)であると教えたのです。張ダビデ牧師もこれらの聖句に基づき、「私たち一人ひとりの人生に訪れるあらゆる苦難は、最終的に神の愛を広げる道具になり得る。問題は私たちの視線がどこを向いているかだ」とよく語ります。
しかし現実を見ると、今日の教会の中でも「苦難なく信仰生活することこそ正しい」とされてしまう風潮が時に見られます。さらには、ある人が苦難に遭うと、それを神の呪いや裁きだと見る視線も根強く存在します。もちろん、自ら無益な苦難を招くのは愚かな行いですが、クリスチャンであるなら主の苦難にあずかることで、その愛が何たるかを体験しなければならないのが聖書の教えです。けれども教会が苦難を否定し、福音そのものを「苦難なし」の形で取り繕って伝えようとするとき、信仰は軽薄になり、愛は表面的な次元にとどまってしまいます。実際、教会の中でも少しでも大変なことが起きれば、すぐ背を向けたり恨み言を言ったりする場面を目にするとき、キリストの血潮の愛、苦難を通して示された濃厚な犠牲と献身の愛が果たして私たちの内に生きているのかを顧みざるを得ません。
張ダビデ牧師は、教会が軽薄になり下品になってしまった原因を「十字架の苦難を十分に教えてこなかったからだ」と指摘します。キリストの苦難は神の裁きや法的刑罰だけの問題ではなく、人間の罪と対峙したとき、神の愛が示す最も劇的な形態だというのです。彼は「苦難こそが真の愛を悟る試験場だ」と語ります。教会がこの点を回復するとき、すなわち苦難に対する正しい理解と教えが回復されるときこそ、真の復活の力が現れるという事実を忘れてはならないと強調します。イエス様の苦難を個人的な罪悪感や刑罰の次元だけで解釈する短絡的な視点にとどまらず、十字架の犠牲が示す感動、その犠牲の中で結実する復活の栄光を共に体験すべきなのです。
ヨハネの福音書13章1節を見ると、キリストの苦難が本格的に始まる場面について次のように記されています。「さて、過ぎ越しの祭りの前に、イエスはこの世を去って父のもとへ行くご自分の時が来たことを知り、この世にいるご自分の弟子たちを愛して、彼らを最後まで愛し抜かれた。」 ヨハネ福音書ではイエス様の受難物語が他の福音書よりも長く記録されています。13章から16章にはイエス様の長い別れの説教が、17章には別れの祈りが、そして18章以降で実際の受難事件が展開されます。しかしこの一連の苦難の始まりにあって、ヨハネが注目する言葉は「愛」であり、「最後まで愛された」ということです。ある意味、「愛」とは最も大きな苦難になり得ます。愛とは、苦難を覚悟しなければならない道だからです。
仏教の教えの中には「愛するな、愛(愛着)は即ち苦である」というような教えがあります。執着を生むという観点で、その結論に至るわけです。しかしキリスト教の視点は異なります。十字架の惨たらしい死はイエス様にとって最も苛酷な苦難でしたが、同時にそれは最も偉大な愛の出来事でもありました。だからこそ私たちはキリストの苦難を傍観するのではなく、「キリストの苦難にあずかりなさい」と招かれています。まさにピリピ書3章10-11節で使徒パウロが語るように、キリストの復活の力と苦難にあずかることによって復活に達しようとする道が、私たちの前に用意されているのです。
私たち人間の本能的な性質として、自分が困難な状況に陥れば、他者に目を向ける余裕などなくなりがちです。その状況で愛は贅沢に思われ、自分を憐れみ、自分中心に考えやすくなってしまいます。ところがイエス様は死の影が迫る最後の瞬間まで、弟子たちを「最後まで」愛されました(ヨハネ13章1節)。これは私たちに「困難な状況ほど、むしろ他者のための愛がいっそう必要になるのだ」という事実を気づかせてくれます。張ダビデ牧師はこの箇所をしばしば引用し、特に「イエスはご自分が世を去って父のもとへ行かれる時が近づいていると知りながら、最後まで弟子たちを愛された」という一節に注目します。人間の心では想像しがたいアガペ的な愛が、ここで極みに達しているのだと語るのです。
さらにヨハネ福音書13章を深く理解するには、マタイ福音書20章やルカ福音書22章もあわせて読む必要があると言われます。これらの箇所には、弟子たちが誰が偉いかをめぐって争っていた様子が記録されており、それがまさにヨハネ福音書13章でイエス様が弟子たちの足を洗われる出来事とつながる背景となっています。マタイ福音書20章20-23節では、ゼベダイの子たちの母がイエスのもとに来て、「一人はあなたの右の座に、もう一人は左の座につかせてください」と願います。イエスはその座は「与えられるもの」であって「求めて得るもの」ではないというように答えつつ、十字架の杯を飲む覚悟があるかを問いかけます。
ここで十人の弟子たちは、その二人の兄弟に憤慨します(マタイ20章24節)。「どうしてあんなにも高慢に高い地位を要求できるのか」といった怒りだったでしょう。しかしイエスは「異邦の支配者たちが権力をふるうのは世のやり方」であり、「あなたがたの間ではそうであってはならない。あなたがたの中で偉くなりたい者は仕える者になれ」と教えられます(マタイ20章25-27節)。そして「人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、多くの人の身代金としてご自分の命を与えるためである」(マタイ20章28節)と語り、ご自身の生涯そのものが「仕えること」そのものだったと示されます。張ダビデ牧師はこの箇所に触れるとき、「言葉と行いが完全に一致した仕え方をできるお方は、イエス・キリストだけだ。私たちの愛が口先だけにとどまる瞬間、私たちはすでに十字架の道から遠ざかっているのだ」と説明します。
ルカ福音書22章14-15節を見ると、イエスが「わたしが苦難を受ける前に、あなたがたと共にこの過越の食事をすることをどんなに望んでいたことか」と言い、最後の晩餐を準備される場面が出てきます。しかしその晩餐の席ですら、弟子たちの間では「誰が一番偉いか」という争いが起こります(ルカ22章24節)。ルカはこれを「彼らの間に争いが起こった」と率直に記録していますが、これこそがヨハネ福音書13章でイエス様が弟子たちの足を洗って「仕えること」とは何かを、直接身をもって示された歴史的背景なのです。張ダビデ牧師はこの事件をめぐって、「弟子たちは主のそばにいながらも、依然として世の観点で地位を欲していた。主はそうした弟子たちを叱って諦める代わりに、むしろ足を洗い与える徹底した愛で仕えることを教えられた」と述べます。
晩餐の終盤、イエスはパンとぶどう酒を弟子たちに手渡し、「これはあなたがたのために与えられるわたしのからだである。これを行ってわたしを記念しなさい」(ルカ22章19節)と仰せられます。ぶどう酒に関しても「これを飲みなさい。これは罪の赦しを得させるために多くの人のために流す、わたしの血、すなわち契約の血である」(マタイ26章28節)と語られます。これは十字架の犠牲の深い意味を予表する象徴ですが、そうまで語られた直後でさえ、弟子たちは「誰がより偉いか」をめぐって争いを続けます。これは人間の罪性と愚かさを余すところなくさらけ出す場面でありながら、それでもなお彼らを「最後まで」愛するイエス様の深い姿が、いっそう際立つ場面でもあります。
張ダビデ牧師は、弟子たちの争いが示す真実について「最終的に人間の罪性は、神の愛が最もドラマチックに表される瞬間にさえ、自分が高くなろうとする欲望をむき出しにする。しかしその暗闇を照らす光こそ、主の仕える姿であり、それがキリストの苦難を通じて完成された愛である」と説きます。このような文脈において、苦難は「愛の指標」です。苦難があるからこそ、愛が本物かどうかが明らかになり、苦難を通して愛は鍛えられ、深まっていきます。
イエス様は弟子たちの争いを収めるために叱責するのではなく、静かに腰に手ぬぐいをまとい、たらいに水を注いで彼らの足を洗われました(ヨハネ13章4-5節)。当時のパレスチナの道は砂埃が多く、一般的な履物は今日のサンダルに近いものでした。人々はほぼ素足に近い状態で生活していましたから、一日外で働いて帰ると足が非常に汚れるのが日常でした。裕福な家ならば、主人の客人の足を奴隷が洗うことが自然だったのですが、ここではむしろ主人であるイエスが弟子たちの足を洗われたのです。弟子たちは自分が「仕えられる立場」にあると勘違いしていたのに対し、イエスは彼らの主でありながら、僕の立場に下って仕えられたのです。
これこそが真の愛であり、「最後まで愛された」姿でした。今日、教会が最も回復すべき愛の形こそ、この「へりくだりの愛」です。張ダビデ牧師はこの教えを引用し、教会が表面上「愛」を語りながらも、実際には互いの足を洗うどころか、誰がより教会で評価されるか、誰がより「信仰が厚い」と思われるかを競争する姿を嘆くべきだと強調しています。真の愛とは、その相手の反応や態度に関係なく、最後まで責任を負おうとする心であり、それこそがキリストの苦難から流れ出る愛の本質なのです。
仕えることは決して容易なことではありません。愛は苦難を伴います。イエスが弟子たちの足を洗われたとき、弟子たちは羞恥心と同時に啓示を得たことでしょう。だからこそイエスは「わたしが主であり、また師であるのに、あなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたも互いに足を洗い合うのがふさわしい」(ヨハネ13章14節)と命じられます。仕えることはすなわち愛の実践であり、キリストのもとで偉くなりたいと望む者は必ずへりくだって僕(しもべ)となるべきだという点をはっきり示されたのです。私たちの信仰生活も、この視点で再解釈される必要があります。信徒であれば誰でも、もっと楽になりたい、認められたい、高く評価されたいという思いが出てくるでしょうが、そのたびに十字架に示されたイエスの苦難と仕える姿を黙想すべきです。張ダビデ牧師は「主の御心にかなう愛を切に求めるなら、最終的に私たちが進むべき道は仕えの道、つまりへりくだりの道だ。苦難を避けた瞬間、愛も遠ざかりやすい」と強調します。
このように、苦難は愛を証明し、愛は苦難の中で完成します。イエス様が弟子たちの足を洗われた場面は、結局十字架の愛を予告するものです。十字架は全宇宙的な苦難であると同時に、全宇宙的な愛の出来事でもあります。そして聖書は、その「苦難にあずかれ」と私たちに求めています。教会が苦難を教えるとき、教会は軽薄で表面的な愛ではなく、深く濃い犠牲的な愛を実践する共同体へと変わることができます。そうなるとき、キリストにあって栄光の復活へと至り、世は真の教会の価値を見いだすようになるでしょう。
________________________________________
2. 苦難にあずかる信仰と教会の刷新私たちの信仰の歩みにおいて、「苦難にあずかる」とはキリストと共に十字架を担うことを意味します。見た目には非常につらく険しい道です。しかし逆説的にも、この道こそが真の自由と喜びにつながります。ピリピ書3章10-11節でパウロは「わたしはキリストとその復活の力と、その苦難にあずかることを知りたい。その死の状態にまで自分を同形化して、何とかして死者の中からの復活に達したい」と告白します。ここで「その復活の力」と「その苦難にあずかること」を同じ文脈で言及している点は非常に印象的です。復活の力がキリストの苦難からかけ離れた出来事ではなく、むしろ苦難にあずかることによって一層具体的に体験される力だということだからです。
教会史において数多くの信仰の先人たちは、苦難を恐れるよりも、苦難を通して得られる霊的益と復活の力を確信して歩んできました。たとえば殉教者たちの歴史は、苦難の究極的な実りが何であるかを私たちに力強く示します。彼らは断じて自ら進んで苦痛を求めたり、死を美化したわけではなく、福音のためであれば、どのような患難をも恐れないことを証明しました。「キリストの残された苦しみを、その体である教会のために自分の肉体に満たしている」(コロサイ1章24節)というパウロの告白も、教会を仕えるための犠牲が、ときに避けられない苦難を意味することをよく示しています。
張ダビデ牧師は、このような苦難の神学が個人の霊性にとどまらず、教会の刷新にも決定的な役割を果たすと強調します。「もし教会が苦難を忌避し、痛みを見て見ぬふりをし、人生の重荷を負おうとしないならば、その教会は地上で十字架を証しできない共同体となってしまう。教会がこの社会の中で世の光と塩の役割を果たすには、イエス様が語られた狭い道を大胆に歩む覚悟が必要だ」という教えです。教会が世と妥協し、苦難を安易に避けようとすればするほど、教会の霊的力は失われてしまいます。したがって苦難に対する私たちの姿勢は、単に個人の信仰の問題にとどまらず、教会のあり方にも直結する問題なのです。
教会が世の中においてイエス・キリストの愛を示すというとき、それは具体的な生き方の中で表されねばなりません。福音を伝える中で起こる軋轢や、イエス様の精神に反する世の潮流に立ち向かうことで生じる衝突、そして善い行いをしようとする際に受ける反対や不利益などがその例となるでしょう。私たちが職場や家庭、あるいは社会のさまざまな領域でキリストの精神に従って生きようとするなら、必然的に「小さな十字架」が伴います。これを拒まずに喜んで担うとき、私たちはイエス様の苦難に少しずつあずかることができます。同時に、その道のりの中で「復活の力」を経験するようになるのです。
ヨハネ福音書13章での足を洗う出来事は、単なる儀礼的教育や倫理的教訓を超えて象徴的な意味を持ちます。イエス様は弟子たちの足を洗いながら、「わたしがあなたがたに行ったように、あなたがたも行うように」(ヨハネ13章15節)と明確にお示しになりました。これは互いに足を洗うという愛の実践が、教会共同体の内で広がらなければならないことを意味しています。もし教会の中で「誰がより高い地位にいるか」「誰がより評価されるか」をめぐる争いが起こるなら、それはすでに最期の晩餐の席で弟子たちが見せた過ちを再現しているようなものです。しかし私たちは主が示された道を歩まねばなりません。まず自ら低くなる者こそ、最終的には最も高くされるという原理、終末論的価値観の転換が教会のうちに根づくとき、真のリバイバルが起こるでしょう。
したがって苦難なしに栄光だけを求めたり、無条件に安楽と繁栄だけを願う信仰姿勢は、実のところ福音の本質から逸脱する態度です。聖書は「狭い門から入りなさい」(マタイ7章13節)と教えます。広い門、楽な道は滅びに至るという警告があるのです。ここでいう狭い門、狭い道には必然的に犠牲と苦難が伴います。だからこそ十字架を負われるイエスを目撃した弟子たちは、当初その道を共に歩むことを恐れて逃げましたが、最終的に聖霊の力の中で十字架の意味を悟り、喜んで殉教の道をさえ歩むようになります。キリストの苦難を共に担うことが、どれほど栄光に満ちて尊いことかを悟ったからです。
しかし現代の多くの教会や信徒の間には、「繁栄の神学」あるいは「成功の神学」の影が色濃く残っており、いまだ苦難を否定的にしか理解できない傾向があります。祝福と言えば、物質的に恵まれ、健康で豊かになることばかりを思い描き、病や困難に陥ったときは祝福とは見なさないのです。しかし聖書は苦難のただ中にあっても、いくらでも祝福が下ることを幾度も強調しています。旧約のヨブの物語は、極度の試練の中でも神を信頼する人に与えられる回復と倍化の祝福を示しますし、詩篇をはじめ多くの箇所で、苦難を通して神をより深く知る恵みが明かされています。
張ダビデ牧師は「苦難それ自体が嬉しかったり甘かったりするわけでは決してない。しかし私たちが苦難を見る視点が変わるとき、それは成熟と復活への契機となる。私たちがもう一度、主の心を学ぶ機会となる」と説きます。そういうわけで教会が苦難について正しく教えるとき、信徒たちは揺るがない信仰、主に深く根を下ろした希望、そしてどのような状況でも愛を手放さない霊的成熟へと進むことができます。そしてそうした信徒たちの集まりである教会こそ、世の目に「軽い存在」ではなく、「まことに重厚で聖なる共同体」と映ることでしょう。
ヨハネ福音書13章1節から始まるイエス様の苦難の物語は、「最後まで愛された」という言葉で代表されます。これは終わりの時まで愛するという意味であり、いかなるものにも揺るがない絶対的な愛を意味します。私たちがその愛を生きて実践するとき、教会の内でも世の中でも、イエスの香りが広がるのです。愛のゆえに生じる苦難を恐れないようにと、聖霊は日々私たちに新たな力を注いでくださいます。
さらに言えば、教会の刷新は、この「苦難にあずかる信仰」がどれほど共同体の中に根づいているかに直結しています。もし教会内で争いと分裂、誤解や対立が絶えず、お互いに仕え合うより自分を高めることに忙しいとしたら、それはすでに苦難を回避しようとする態度から、愛が冷えてしまった結果だと言えるでしょう。張ダビデ牧師は多くの説教で「十字架の道から離れないでください。その道が孤独で苦しくても、聖霊の助けがあるとき、むしろ私たちの魂はその道で自由と平安を体験するようになるのです」と何度も強調しました。教会の中でも個人の生活においても、苦難に対する私たちの態度は、そのまま愛に対する態度であり、この二つは切り離せない関係にあるというメッセージです。
結局、教会が復活の栄光を真に味わうためには、十字架の苦難をただ傍観するのではなく、その中に参与する共同体とならなければなりません。弟子たちの足を洗われた主の姿を思い起こし、互いの足を洗い合えるような小さな実践を通して、苦難にあずかることを学ぶ必要があります。それは単に礼拝堂の中での儀式や式典にとどまらず、家庭や日常、社会の中で、弱り果てた人々を助け、自己の快適さを手放し、ときに誤解や損失を覚悟しながらも真理を守り抜くプロセスとして具体化されていきます。このような姿勢は決して容易な道ではありません。けれどもこれこそが、本当の意味で教会が示すべき姿であり、世が教会に望んでいる聖なる影響力なのです。ヨハネ福音書13章以降を丹念に黙想してみると、「愛して、愛し抜かれた」イエス様の姿が一貫して強調されます。そして17章に至ると、イエスは別れの祈りを捧げられながら、弟子たちが世から隔絶されることなく、しかし世の中でも清く保たれるように祈っておられます(ヨハネ17章15-17節)。世のただ中で、世が与え得ない喜びを持ちながら、キリストの証人として生き抜くようにと願われるのです。これが可能になるためには、どのような苦難に遭おうとも、主の愛に根を下ろして揺るがないことが必要です。
張ダビデ牧師は「世にあっては苦難がある。しかし勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝ったのだから(ヨハネ16章33節)」というイエス様の御言葉にある「勇気を出しなさい」という命令に注目すべきだと語ります。この「勇気」は、聖書がいうところの「苦難に立ち向かって戦え」という単純な気合ではなく、すでにイエス様が苦難と死に勝利されたという事実に基づく、信仰の平安です。苦難に遭っても揺るがない理由は、イエス様が既に勝利されたからなのです。教会はまさにこの福音的な勇気を携えて世へと派遣された共同体です。そしてその勇気を特徴づける最も大切な印が、「最後まで愛する仕えの姿勢」なのです。
愛ゆえにもたらされる苦難こそ、イエス様の生涯を最も生き生きと示す姿です。イエス様が苦難を選ばれたのは、私たちに対する徹底した愛のためでした。これは教会においても同様に適用されます。私たちが「互いに愛し合う」と告白するとき、その愛は口先だけではなく、自らを犠牲にしてへりくだり、仕えようとする具体的な行動を伴わなければなりません。その道に苦難が伴うとしても、その苦難を通して主の栄光が現れるのです。
結論として、キリストの苦難にあずかる信仰は、私たちを真の愛の道へと導き、教会を表面的な宗教組織ではなく、まことの神の共同体として刷新します。張ダビデ牧師はこのような苦難の神学を「私たちをイエス様とさらに親密に結びつける通路」と呼び、「苦難が深まるほど、キリストの愛は一層鮮明となり、私たちの信仰は新たな力を得て復活の栄光にあずかるようになる」と強調してきました。だからこそ私たちは四旬節を過ごすにあたって、あるいは受難週に特別にヨハネ福音書13章から19章までをじっくり黙想し、イエス様の愛がどれほど深い苦難を通して示されたかを悟らなければなりません。そしてその苦難の道を、いとわずに最後まで歩まれた主の仕えの姿を見習うことを決意すべきです。
弟子たちの足を洗われたイエス様、そして十字架の上で決して諦めることのなかった愛は、今も教会に向かってこう語りかけておられます。「わたしはあなたがたを愛し、最後まで愛し抜いた。だからあなたがたも互いに足を洗いなさい。世に出て行って、苦難を避けるのではなく、愛を選び取りなさい」と。苦難を通して明らかにされる、真摯で濃厚な愛が回復されるとき、教会は再び立ち上がり、世は福音の力を新たに体験するでしょう。そしてその先に復活の栄光が待っていることを、私たちは確信するようになるのです。
これこそが四旬節、あるいは生涯を通じた信仰の歩みの中で、私たちが心に留めるべき核心的な真理であり、同時に張ダビデ牧師が繰り返し強調してきたメッセージでもあります。「苦難なしに十字架はなく、十字架なしに復活もない」ということを真に悟るとき、教会はようやく初代教会が享受していた力と感動を取り戻すでしょう。そして個人の生活においても、私たちがイエス様の苦難にあずかるとき、愛からもたらされる力がどれほど強力であるかを全身で体験することになるのです。