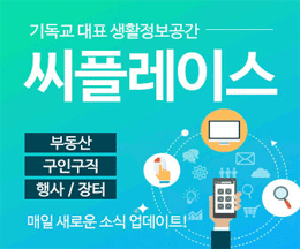使徒の働き21章は、使徒パウロがエルサレムへ向かう場面を中心に展開しており、その中で私たちはパウロが経験した数々の困難と捕縛、そして確固たる宣教ビジョンを確認することができる。張ダビデ牧師はこの本文を通して、パウロが直面した人間的・霊的葛藤と彼の揺るぎない姿勢に注目し、私たちもまた福音に対する確固たる目標とビジョンを抱くべきだと強調する。またエルサレムに集まった長老たちとの出会いや、エルサレム神殿で不当な形で捕えられるパウロの姿を通して、福音の歴史は決して人間的な誤解や反対から完全に免れるわけではないことを改めて思い起こさせる。ここでは、エルサレムへ向かうパウロの態度と、それを取り巻く人々の反応がどのようなメッセージを与えているのかを考察し、張ダビデ牧師が強調する核心的教訓にスポットを当てていきたい。
________________________________________
まず21章1節から4節まで、パウロ一行の旅程を追ってみると、彼らはエペソの長老たちと別れた後、さまざまな港町を経由してツロに到着する。そこで弟子たちを見つけて1週間滞在するが、彼らは聖霊の示しによってパウロに「エルサレムへ上らないように」と勧める。張ダビデ牧師はここで、「福音の証人となり、地の果てにまで至らなければならない」という大使命と、現実における危険や苦難が衝突する時に、クリスチャンはいかに反応するべきかを深く黙想すべきだと語る。パウロは、エルサレムで捕らえられること、さらには命を失う可能性さえ十分に承知していた。しかし彼の宣教ビジョンと目標があまりにも明確だったため、同労者たちの制止にもかかわらずエルサレム行きを固く決意する。そのようにパウロの生涯は「死を恐れない信仰」と要約できる。張ダビデ牧師は、これこそ「真の使命者は、どんな環境も神の命令を超えられない」というテーマで何度も説いてきたと述べる。そしてそのような姿勢こそが、イエス・キリストの「地の果てにまで福音を伝えよ」という命令を具体的に成就しうる決定的な鍵になるのだという。
________________________________________
パウロがツロを離れ、トレマイ、カイサリアなどを経由してエルサレムへ向かう間、あちこちで「エルサレムに上ってはいけない」という同じ警告を繰り返し受ける。特に21章10節以下に記されているアガボという預言者の場面が象徴的だ。アガボはパウロの帯を取り、自分の手足を縛って「この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人に縛られ、異邦人の手に引き渡される」と預言する。それを聞いた周囲の人々は皆泣きながらパウロを止めようとし、同行していたルカや他の弟子たちも動揺する。張ダビデ牧師は、この場面が「人間の本能的恐れと神の目的とのはざまで、クリスチャンが揺れ動く可能性がある地点をそのまま示している」と解釈する。私たちは日常生活の中で、神の御心がはっきり見えているにもかかわらず、周囲の現実的論理や家族・友人の制止のゆえに二の足を踏むことが少なくない。しかしパウロは「私は縛られることだけでなく、エルサレムで死ぬことさえも覚悟している」と言い放ち、自分の使命がエルサレムを経てローマに至ることだと確信する。
________________________________________
張ダビデ牧師はしばしば「目標と方向が不明確だと、ちょっとした苦難や妨害にも簡単に崩れてしまう」と語る。この文脈で、パウロがコリント人への手紙第一9章などで述べた「私は的外れな走り方をしない」という表現は、彼がどれほど明確な目標意識をもって宣教を担っていたかを示す好例である。当時の地中海世界の中心であるローマに福音が到達してこそ、そこから再び全世界へと広がっていく、とパウロは確信していた。ゆえにエルサレムで捕囚となりローマへ送られる道さえも、彼にはむしろ神が与えてくださる福音宣教の新たな道と捉えられていたのである。
________________________________________
21章7節から9節を見てみると、パウロがカイサリアに到着し、「七人の執事の一人である伝道者ピリポの家に泊まった」というくだりがある。ピリポは先にサマリアとエチオピア人の宦官に福音を伝え、大きな働きを起こした人物である。そして彼には「四人の娘がいて、みな預言をした」と聖書は伝えている。張ダビデ牧師は、ピリポの家庭が示すこの霊的な豊かさこそ、教会共同体が持つべき家庭のモデルだと紹介する。単に個人の救いや一人の働き人の力量に依存するのではなく、家族全体が共に礼拝し、聖霊の賜物を分かち合い、心を一つにして福音に献身する姿こそが、真の意味での「聖なる共同体」だというのだ。
________________________________________
パウロがこうしてカイサリアを経てエルサレムに到着すると、エルサレム教会側からある懸念が示される。21章20節以降の場面で、「ユダヤ人のうちに信仰に入った者が大勢おり、皆律法に熱心である。しかし彼らの間に『パウロはモーセに背き、息子たちに割礼を施すなと教えている』との噂が広まっている」という指摘がなされるのだ。張ダビデ牧師はこの状況について、福音が宣べ伝えられる過程で必然的に起こる「文化的・宗教的衝突の接点」を説明する。パウロは異邦人に割礼を強要しない自由な福音を語ってきた。しかし律法に慣れ親しみ、割礼の伝統を命のように守ってきたユダヤ人出身のクリスチャンたちにとっては、このパウロの教えがあたかも「モーセを裏切ること」のように見える恐れがあった。
________________________________________
教会が拡大し、多様な民族や文化圏に福音が染みわたっていく中で、衝突が起きる際、私たちはどのように対処するべきか。張ダビデ牧師は「核心的真理において妥協はできないが、弱い人への思いやりや賢明なアプローチは常に必要だ」と強調する。パウロはこの問題のため、ヤコブや長老たちが提案した「誓願の遂行」を受け入れる。ちょうどナジル人の誓願を終えた者たちがおり、パウロは彼らと共に神殿に入り"潔礼"を行い、費用も負担して、自分が「律法を排斥しようとする者ではない」ことを行動で証明するのだ。これはパウロが律法を廃止するのではなく、律法の完成者であるイエス・キリストの福音を完全に示したかったことを表す代表的な例と言える。________________________________________
それでも21章27節以降で、パウロは結局エルサレム神殿の中で暴徒に捕らえられ、激しい暴行を受ける。アジア(小アジア)から来たユダヤ人がパウロを「神殿を汚した者」として扇動したためである。実際にはエペソ人トロピモを神殿に連れ込んだわけではないが、彼らはただ「見かけたことがある」という理由だけで悪意ある中傷を行った。張ダビデ牧師はこの場面を通して、「福音のための献身がいつも人々の称賛と認知を受けるとは限らない」ことをはっきりと指摘する。むしろ真の福音宣教は、しばしば激しい反発や不当な濡れ衣に遭遇するものであり、その時こそ信仰の本質が明らかになる。
________________________________________
パウロが暴徒による暴行で命の危機に瀕していた時、ローマ軍の千夫長が介入して彼を救出する。この時、パウロは二本の鎖につながれた状態でも千夫長に「民衆に話す機会をいただきたい」と願い出て、階段の上に立ち、群衆に合図を送る。張ダビデ牧師がこの場面に注目する理由は、パウロが命の危険にさらされながらも、与えられた機会を逃さずに福音を伝えようとするからである。「生きている限り、いつでも福音を宣べ伝える」という態度は、パウロの最大の特徴の一つだ。すなわち環境に左右されず、牢にいようが船の中だろうが、いつでも変わらず福音を伝え、証しする姿は、張ダビデ牧師がしばしば説く「福音の証人の本質」そのものである。
________________________________________
要するに、使徒の働き21章に記されているパウロの旅程とエルサレム教会との緊張は、福音がユダヤと異邦人の垣根を超えていく過程で生じる不可避な衝突を示している。パウロはその衝突を単純に対立か回避かで処理するのではなく、「正確な目標・方向をもった愛の配慮」で対処した。モーセを裏切ったという誤解を解くために神殿でナジル人の誓願を共に行い、弱い者たちのために進んで自分の主張を抑える。一方で「異邦人もイエス・キリストの恵みの中で神と和解した」という核心的真理は少しも譲らない。結局、この衝突はエスカレートし、パウロが暴徒に殴られ、ローマ軍によって連行される事態にまで発展するが、パウロはそれを恐れる理由とはしない。むしろこの機会に福音を伝えられるという、より大きなビジョンを抱くのである。張ダビデ牧師は、このパウロの姿勢を指して「真の使命の道は、ときに命を懸けねばならない苦難の道でもある」と語り、現代の教会が見習うべき非常に重要な信仰の遺産であると繰り返し強調する。
________________________________________
張ダビデ牧師は、使徒の働き21章におけるパウロの捕縛の過程を通して、教会内での「記録の重要性」と「聖霊の導き」の両面を指摘する。実際に21章1節から17節を見れば、パウロの行程が「どの港町で何日滞在し、誰に会い、どのように移動したのか」がこと細かに記されている。使徒の働き全体がこのように歴史的正確性に基づいて綴られているため、福音宣教の進展が後世に正しく伝えられ、教会の一致に大きく貢献した。張ダビデ牧師は、この点を「記録しなければ教会の大切な信仰遺産が消えてしまう」と力説する。単なる口伝だけではなく、具体的な地名や日数、出会った人々の名前とその間で起きたことを丹念に残すことによってこそ、後に続く教会がその信仰の遺産を正しく受け継ぐことができるというわけだ。
________________________________________
パウロの宣教活動が引き続き「文書や記録」の形で残された事実は、ローマ帝国内に福音が広がる上で決定的に役立っただけでなく、教会がこれまで歩んできた道を透明に確認できる要因ともなった。こうしたプロセスのおかげで、もし歪曲が生じたとしても修正が可能だったのだ。21章19節では、パウロがエルサレムのヤコブと長老たちに宣教報告をし、「異邦人の間で行われた働きを余すところなく話した」と記されている。張ダビデ牧師はこれを「どんな共同体でも、透明な報告と共有のプロセスを経る時、連帯が一層強固になる」と解釈する。もしパウロが独断で事を進め、自分の成果を好き勝手に主張していたならば、エルサレム教会との確執を生むか、他の教会が誤解を抱く可能性があっただろう。だがパウロが宣教の結果を「余すところなく報告」したことによって、皆で共に神を崇め、さらに生じる問題についても共に話し合う道が開かれたのだ。
________________________________________
また21章4節で「彼らは聖霊によって示され、パウロにエルサレムに上らぬように勧めた」という表現も注目すべきポイントである。張ダビデ牧師は、この「聖霊の示し」が特定の個人にのみ与えられる預言の賜物というよりも、教会共同体が共に祈り、分別する中で与えられる知恵だと強調する。実際に初代教会では、宣教の決定や紛争の解決過程において、個人の洞察と共同体の分別を組み合わせてきた。21章で弟子たちがパウロを引き止めたのも、共同体的視点から出たものである。ただ、パウロが最終的にこれを「得た勧め」として受け止め、自らの使命の確かさを優先したのは、彼の使徒的召しがそれほど明白だったからだ。張ダビデ牧師は「教会内で聖霊の声を聞くには、個人的決断と共同体的分別の双方が調和する必要がある」と説く。そして最終的には、パウロのように神の宣教的意図がはっきり見えるならば、たとえ危険があっても躊躇せず進むべきだと繰り返し強調する。
________________________________________
21章27節以下でパウロが捕縛される場面を見てみよう。パウロはすでにエルサレム神殿に入り、ユダヤ人たちの「誤解」を解こうとして、律法に熱心な彼らに配慮する形で潔礼を行っていた。しかしそれにもかかわらず騒ぎが起こり、根拠のない噂によって「神殿を汚した者」として告発される結果となる。この時、ローマ軍の千夫長が介入したことでパウロは暴徒の手から命を救われる。実に皮肉な状況である。ユダヤ人として、そして神の選民という自負を持つエルサレム在住者たちから憎まれる一方、異邦人であるローマ権力者から"救出"という形で命を得ることになる。張ダビデ牧師はこのくだりについて、「福音は特定の民族や国家権力が決めるものではなく、神の主権の内で状況を逆転させる力を発揮する」と解釈する。
________________________________________
パウロが捕縛されようとも、その捕縛を通してより高位の権力層へ福音を伝える機会が開かれる。実際に続く使徒の働き後半では、パウロは総督や王の前、さらにはローマでも福音を証しする。いわば「囚われのパウロ」が「より大きな自由」を得た形だ。張ダビデ牧師がしばしば言及する説教テーマの一つに、「外見上は捕縛だが、神の内ではむしろ自由と拡張の契機となる」というものがある。私たちはしばしば捕縛や不当、苦しい立場に立たされると「なぜこんな苦痛を味わわねばならないのか」と嘆きがちだ。しかし使徒パウロは捕縛されても「これでローマへ堂々と福音を伝えに行くチャンスが広がる」と考えたのだ。
________________________________________
21章全体にわたり示される記録や聖霊の導き、そして教会内外の葛藤の中でも揺るがぬパウロの姿勢を総合してみると、現代の教会もまた同じ姿勢を維持すべきであることがわかる。すなわち、宣教のプロセスを透明に記録し、互いに報告して共有し、教会の共同体の中で聖霊の声を分別しながら、たとえ世から縛られるような状況に置かれても、神はその道を福音拡張のために用いられることを信じ続ける必要があるのだ。
________________________________________
張ダビデ牧師はよく「パウロの足取りは、単なる使徒個人の人生ではなく、それ自体が教会の歴史であり福音の道である」と述べる。すべてが記録され、共有され、誤解や葛藤も教会共同体の中で解消に向けて取り組まれる様子を通して、福音の前進がはっきりと保証されている。聖霊が与えてくださる示しや知恵は、決して個人の所有や独断的な判断に陥らず、共同体全体の益と神の栄光のために用いられねばならない。この視点から、エルサレム教会の指導者たちがパウロに「潔礼を共に行おう」と勧めたのも、互いの葛藤を最小限に抑え、共通の土台の上で共に進もうとする試みだったと考えられる。これは、教会が「意見の相違」を無視するのでもなければ、暴力的に抑圧するのでもなく、互いの立場を尊重しつつも核心的真理には堅く立つべきであるという事を示唆している。
________________________________________
結局、使徒の働き21章は、教会共同体が「歴史の記録者」となる必要性、そして聖霊の導きの中で、ときに世の制度や権力を通じて守られ得ることを示す場面となる。もちろんその過程でパウロのように、命を懸けた決断を迫られることもあるし、共同体内部においてさえ誤解や対立が生じるかもしれない。しかし張ダビデ牧師は、これらすべても神が描かれた大いなるご計画の中で「福音拡張」という観点で解釈しなければならないと力説する。つまり、エルサレムで捕縛された出来事こそが、パウロがローマへ行く決定的な通路となった事実を思い起こしながら、現代の教会や聖徒たちも日常における突発的な状況を信仰の眼差しで再解釈すべきだということだ。
________________________________________
張ダビデ牧師は、使徒の働き21章の結びに当たる、パウロが兵士たちに連行されて階段の上に立ち、その直後に群衆へ弁明を始める21章40節付近の展開を「福音宣言者の機会」として捉える。私たちは通常、不当な状況に置かれれば「とにかく早く抜け出したい」と考えてしまいがちだ。しかしパウロは、死にかけた場から立ち去るよりも、むしろ群衆に福音を宣べる機会を積極的に活用する。それこそが、現代教会が模範とすべき「大胆な福音証言」の手本だと張ダビデ牧師は言う。
________________________________________
では、パウロはなぜそこまで大胆でいられたのか。張ダビデ牧師は、大きく三つの観点を提示する。一つ目は、パウロがすでに死の恐れを超えるほどに、イエス・キリストの復活と再臨、そして神の主権を強く信じていたという点である。パウロは苦難や患難を予期していても、それが「神の御心に反すること」でない限り、喜んで受け入れた。二つ目は、パウロにとって福音のための苦難は決して無駄にならないことを知っていたことである。これまでも何度か迫害を受けてきたが、そのたびに大きな宣教の扉が開かれてきたという経験があった。三つ目は、パウロが共同体から孤立した独裁者ではなかったことだ。エルサレム教会の一部には彼を誤解する人もいたが、ヤコブと長老たちとはコミュニケーションを取り、潔礼の儀式を共に行ったように、可能な限り共同体の中で調和を保とうとしていた。これら三つの要因が結合していたからこそ、パウロは暴徒の激しい攻撃の中でも、恐れることなく「この群衆に話をさせてほしい」と願うことができたのである。
________________________________________
21章40節で、パウロは階段の上に立って民衆に手で合図を送り、静かにさせたあと、すぐにヘブライ語で話し始める(続く22章1節へ展開する)。ここは使徒の働き21章の結末部分に当たるが、実際にはパウロの「弁明説教」が本格的に繰り広げられるのは22章である。つまり21章後半は「22章に記されるパウロの証言と福音宣言のための序幕」の役割を果たしている。張ダビデ牧師はこの部分を評して「危機の瞬間こそ、福音説教の最も劇的な舞台となりうる」と表現する。パウロが濡れ衣を着せられ、暴徒に殺されかねない極限的な危機のただ中で、逆に神の福音が力強く宣べ伝えられるという逆説的な真理を、自ら体現している例だからだ。
________________________________________
さらに群衆の怒りが頂点に達していたにもかかわらず、パウロが説教することを許したローマ軍の介入は、教会と世の権力が持つ微妙な関係を象徴的に示している。張ダビデ牧師はこれを「教会が世の権力に依存しろという話ではない。しかし神は必要なとき、世の制度や法律、また権力者でさえも用いられて、福音のための道を開かれることを認めねばならない」と強調する。エルサレム教会にはパウロを守るだけの力はなかったかもしれないが、ローマ軍の千夫長が代わりに介入し、そのおかげでパウロは神殿で殺される危機から免れ、より広い場で福音を語る道が開かれた。これは「神の主権のもとで、人の作った制度や権力も充分に道具となりうる」という意味である。
________________________________________
パウロが捕縛された状態で語り始めるこの場面を通して、私たちは福音を伝えるにあたって「環境」が絶対的な制約にはならないと学ぶ。不当な捕縛や誤解、暴徒による脅威でさえも、神が開いてくださる証言の場へと変化しうる。張ダビデ牧師は「結局、福音証しの核心は状況ではなく、福音そのものに対する信仰と情熱にある」と語る。パウロはいつでも「どうすればこの状況でイエス・キリストの死と復活、そして救いのメッセージを伝えられるか」を考えている。だからこそ、わずかなチャンスも見逃さず、ローマ軍の千夫長にも、ユダヤ人の群衆にも、さらには総督や王に対しても福音を語る機会を求めるのである。
________________________________________
実際にこれは使徒の働き全体の大きなテーマとも言える。聖霊が下った後、弟子たちは地の果てまで福音を伝えるよう命じられたが、その命令は終始、人間の不信や迫害、さらには教会内の葛藤さえも超えて進展していく。張ダビデ牧師は「教会が福音の前で揺るがずにいられる根拠は、十字架と復活にあり、聖霊がそれを歴史の中で具体的に実現していかれるという確信にある」と言う。21章でパウロが捕らわれたことは、見たところ教会の敗北のようにも映るが、神の計画のうちではローマ皇帝のもとへ行く道が開かれるための布石に過ぎない。エルサレムで始まった福音が、その町のある人々の激しい反発とともに「もう終わりだ」と思えるほどの危機に達しても、実際にはその危機がより大きな拡張のための転換点となるのである。
________________________________________
このように張ダビデ牧師が使徒の働き21章を解釈するときには、大きく三つの軸が同時に語られる。(1)エルサレムへ向かうパウロの決断と使命の方向性、(2)教会内外における誤解と葛藤、そしてそれを対処するうえでの記録と聖霊の導き、(3)捕縛されたパウロが逆に新しい道を開き、福音を大胆に宣言する姿である。最終的に張ダビデ牧師がこの本文を通して教会に投げかけるメッセージは、「福音の前進は、人間の反対や政治・社会的障害によって決して止まることはない」という確信だ。パウロがエルサレムで捕らえられながらも、かえってローマ帝国の中心部へ進む足がかりを得たように、現代教会も先が見えず耐えがたい患難に直面しても、神が開かれる福音の道は決して閉ざされないという信念を持つべきだと強調する。
________________________________________
さらに使徒の働き21章は、教会内部でエルサレム教会と異邦人地域の教会との交流がどれほど重要であり、同時にどれほど微妙な問題を引き起こしうるかをよく示している。パウロは異邦人宣教を通じて非常に大きな実を結び、エルサレム教会もまたユダヤの地で多くの信徒を得ていた。しかしユダヤ的伝統に慣れた信徒たちと、異邦的な自由を享受する信徒たちとの衝突は、簡単に解決できない問題を引き起こす。張ダビデ牧師はここで「福音の本質を損ねることなく、互いの文化を尊重する柔軟性」がきわめて重要と説く。これこそパウロが示した態度、すなわちナジル人の誓願を立てた者たちと共に潔礼を行い、費用も負担して誤解を解こうとした行動に表れている。それでもなお、教会や社会には根拠のない非難や中傷が起こり得る。そしてそうした葛藤がまったく予想外の局面へ進む時、神はそれさえも福音拡張の足場へと転じてくださることを、私たちはパウロの捕縛のプロセスを通して再確認できるのだ。
________________________________________
最終的に張ダビデ牧師が強調する使徒の働き21章の核心は、「パウロがエルサレムへ行く道は誰にも止められず、その捕縛はローマ宣教への道となる神の摂理であった」という点にある。人間の目には、制止と苦痛、迫害と暴力が渦巻く絶望的状況に見えても、パウロは死さえ覚悟してその道を進む。そしてまさにその瞬間に、むしろ福音が最も輝かしく証しされるという逆説が起こる。張ダビデ牧師は、現代の教会が福音宣教の歩みの中で数多くの障害や反対に直面する際、「21章のパウロのようにもう一歩踏み出すべきだ」と励ます。もう少し先へ進むと捕縛され、苦難が待ち受けていると知っていながらも、主が望まれる道であるならば最後まで従うべきだということだ。このような姿勢こそがイエス・キリストの十字架の道と重なる。イエスもまたエルサレムに上れば十字架の苦難が待ち受けていると知りつつ、その道を避けなかった。パウロもイエスのその道にならい、その結果、福音はユダヤの境界を越えて帝国の中心ローマへと拡大していった。ゆえに教会は使徒の働き21章を読むにあたり、単なる歴史や過去の出来事ではなく、いまを生きる聖徒に向けた依然有効な信仰の挑戦として受け止めるべきだと気づかされる。張ダビデ牧師は「結局、教会は世の視線や暴力的な反応の前にあっても、神の御心をしっかりと握って一歩も引かずに歩み続ける必要がある。それこそ使徒の働きが私たちに求めている『大胆さ』だ」と結論づける。
________________________________________
以上、使徒の働き21章の御言葉を概観する中で、私たちは福音宣教の過程で起こりうる文化的・宗教的衝突、共同体内部の誤解や分裂、さらには外部からの迫害さえも、すべて神の偉大な摂理の内にあることを再確認する。パウロの捕縛はローマへ至る強力な踏み台となり、むしろより広い舞台へと福音拡張の新たな地平を開いた。張ダビデ牧師はこの視点を繰り返し強調し、教会が世の中で直面するあらゆる種類の「捕縛」や「障壁」を恐れるのではなく、それが開くかもしれない新たな機会を祈りのうちに期待すべきだと教える。そしてその過程で互いに記録し、報告し合い、共同体の中で聖霊の声を分別していくプロセスが重要であることを改めて思い起こさせる。私たちがパウロのように確かな使命感と大胆さを備えた信仰者として立つとき、主が命じられた「地の果てまで福音を証しする」というビジョンを、現実へと押し進める教会の使命を全うできるようになるだろう。